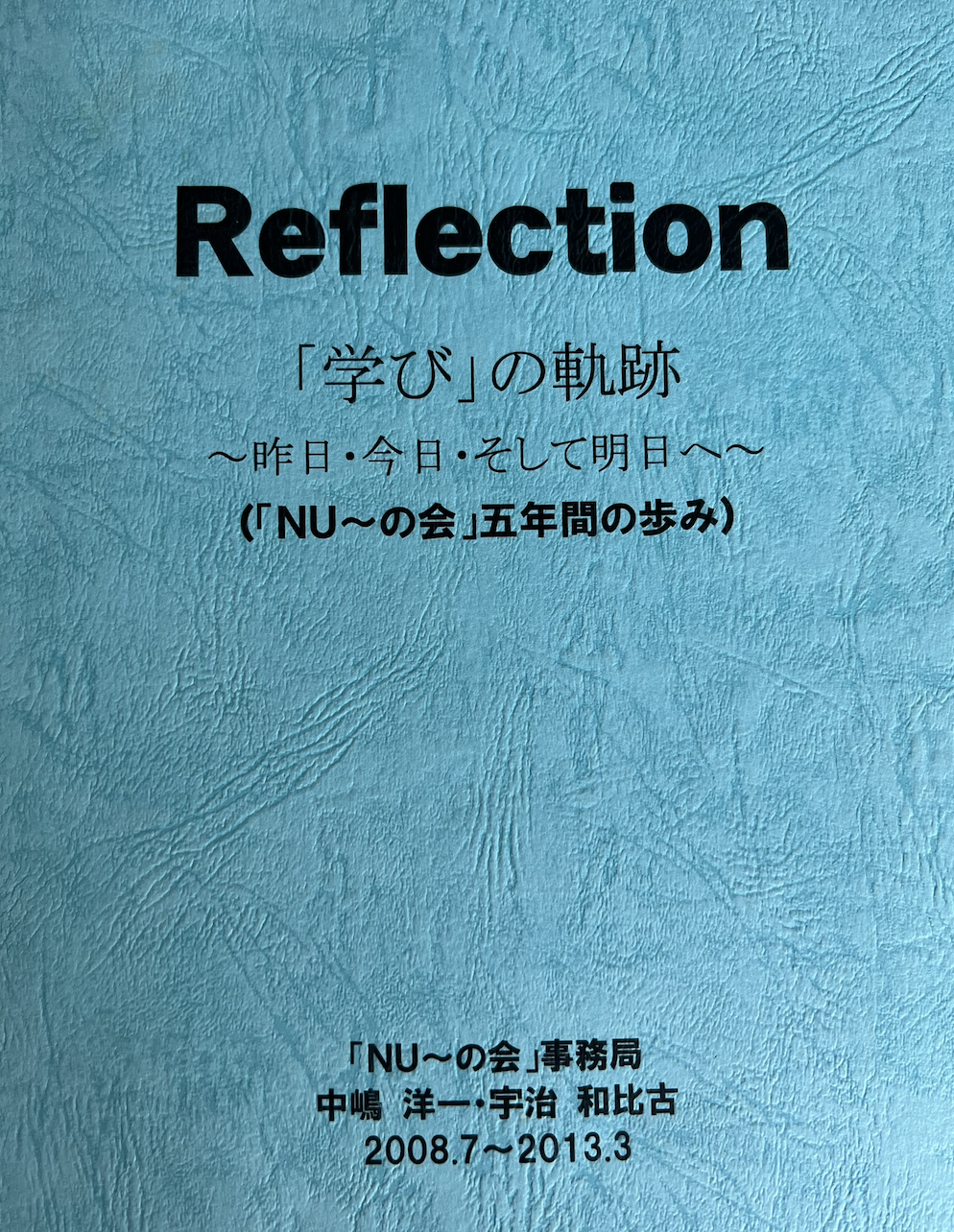ミスや失敗の活かし方を学ぶ
アイキャッチの画像は、前にもご紹介した「NUの会」(全ての校種、教科を対象とした関西圏の勉強会)のまとめです。タイトルは”Reflection”となっており、うまく行かなかったことを洗い出し、そこから何を学んだのかを丁寧に記録した冊子です。今回のテーマを考えた時に、真っ先に浮かんだのがそれでした。
さて、タイトルの英文の意味は次の通りです。
「自分にとって最高の教師は、自分が犯した直近のミス。人生に失敗はない。それを経験(教訓)として、次のステージに繋げていくことが大事である」
これを日々の授業に置き換えてみると、次のようにならないでしょうか。
「信頼できる教師は過去の自分。自分の取り組み(直近の授業)を振り返ることが成長につながる」
書籍やセミナーなどで得る情報も大事ですが、実際にやってみて何が問題だったのかを言語化しなければ、「学んだ」ことにはなりません。短時間で「正解」を求めるような授業では、教師の「違う」「他に?」「はい、次」といった「言刃」が横行するようになり、学習者はmistakeやerrorを「恥ずかしい」と思うようになります。
一方、教師が「間違いから学ぶことの方が多い。人は間違えれば、それだけ賢くなれる(More you make errors, more you can learn. )」というスタンスで学習者に接していると、彼らの心は開放されます。間違えた子どもに対して、「ありがとう。おかげでみんなが深く学べたね」と感謝する教師のクラスでは、発表する仲間の言葉を明るい表情で傾聴する子どもたちが育ちます。
そのようなクラスでは、「みんなで学ぶのが楽しい」という思いが広がっていきます。楽しいことは続けられます。やがてそれは習慣となり、力になり、自信となります。
生徒と一緒に「教科書」をカスタマイズ(またはリバイズ)する
前の授業でうまくいかなかったことをうやむやに(そのままに)してしまうのは、「決めた時間で終わるために、先に進まなければいけない」という考え(典型的なTask on time)がベースにあるからです。
実際、「生徒が熱心に授業に取り組まない、集中しない」という悩みを抱える若い先生が多いようですが、授業の進め方云々よりも、課題そのものにワクワクしていないのではないかと考えてみることが大事です。そのような「視点」は、適宜、アンケートなどで生徒の実態(力がついた活動とそうでなかった活動、夢中になってやれた単元とそうでなかった単元など)を確認することで身につきます。すると、「授業を行う立場」ではなく、「授業を創る立場」になれます。
教科書とは、そもそも「素材」であり、そのままでは「教材」にはなりません。生キャベツ(食材)と同じです。生キャベツが欲しくなるとき(トンカツなど)もありますが、基本的に、それぞれの単元を野菜炒め、ロールキャベツ、ポトフ、回鍋肉などの料理に変えてやることが大事です。生徒が夢中になる授業で必要なのは、自分ごとになる「課題」であり、自ら考えたくなる教師の「発問」です。それが用意されて、初めて教科書という「素材」がワクワクする「教材」になります。
教科書に載っているタスク、練習や言語活動は、いずれも生徒にとって必要感があり、やってみたくなるというものばかりではありません。採択された一社の教科書だけを見ていると、「全て教えなければならない」「この通りにやらなければならない」という思い込みが生まれてしまいます。しかし、他社の教科書を用意し、並べてみると、そのスタンスの違いに驚かされます。「ああ、こんなやり方もあるんだ」「こっちのタスクの方が生徒は乗ってきそうだ」というものも見つかります。不思議に思って学習指導要領を読んでみると、いろんな解釈、多様な活動が可能であることに気づけます。あくまでも、拠り所は学習指導要領なのです。
教師は、学習指導要領に書かれていることを正しく理解し、学習者の実態に応じて、教科書を臨機応変にカスタマイズしていくことが必要です。その力をつけるためには、複数の教科書(新聞と同じで驚くほど違います)を手に入れ、編著者たちの様々な考え方、練習方法、思考ツールを使った指導などを知ることです。
そして、生徒にも「どこを変えれば面白くなりそう?」と尋ねてみるのです。彼らは受け身の授業では暗い顔をしていますが、自分ごとになった活動、自分たちのオリジナリティが活かせる授業では目をキラキラさせます。ですから、生徒たちの応援(アイデア、支持)を支えに、勇気を持って自分なりに教科書を「味付け」してみるのです。「教科書通りに進める」ことに辟易としていた生徒たちは、「ワクワクする授業」を求めて「遊び心」を発揮するようになります。それが、「生徒を主体にした授業」です。
そのような取り組み(授業)を積極的に他者に公開し、自分の考え方(教科書をrevisedした取り組み)を客観的に評価してもらうことです。他者評価に裏付けられた自信は、やがて確かな授業力となります。
違和感のセンサーが高まれば、授業力も高まる
違和感が生まれるのは、自分がゴールとする実像(生徒の育った姿、何がどこまでできているかが具体になった姿)を頭に描かれている場合です。教科書を先に進める授業では、生徒指導面では気になることはあっても、「育った姿」に対する違和感は生まれてきません。部活動の指導でも「変だ」と咄嗟に感じることができるのは、育てたい選手像ができているからです。
自分が違和感を持ったことに対して、「違和感が生まれたのは何故か」とマンダラ・チャートの中心に書き、思い当たることを書き出してみると、「待てよ」「もしかして」「そうかも」というひらめきが生まれてきます。日頃から、そのセンサーを高める努力をすることです。
問題に向き合うことで、今まで見えなかったことが見えるようになります。問題は「生徒側」にあるのではなく、教師側の「指導方法」にあったのではないかと「視点」を変えた時、初めて自分の授業の「腕」がワンランク上がります。授業力が高まるとは、教師が今までできていなかったことが、実際にできるようになることだからです。
書籍で読んだことをやってみたり、どこかのセミナーで聞いたことをやってみたりする場合、うまくいかないことの方が圧倒的に多くなります。なぜなら、クラス(生徒)の実態が違うからです。黒か白か(できた、できなかったか)という判断ではなく、うまく行かなかったことをきちんと言語化して残しておくこと、生徒の感想(どこができなかったのかというモヤモヤ感)から、どんな要素が原因として考えられるかを省察しておくことが大切です。
それによって、次回、何かに取り組むときに、それが全体構想(事前の計画)の「チェックポイント」になるからです。
授業力を高めるのは「自己内対話」
「授業力」を高めるには、「自己内対話」ができることが肝心です。「本当にこれでいいのか?」という問題発見をしなければ、人は「変わりたい」とは思わないからです。
書籍に書かれていること、セミナーで聞いたことに飛びつくのは、自分の現在地(雑草が生えている庭)を認識せずに、隣の芝生(他者の実践や指導技術など)を羨ましがるようなものです。それでは、自己理解が深まらず、「自己内対話」は生まれません。やがて、自分の授業を客観視できないまま授業をするのが習慣になってしまいます。
当HPの「『階層式マッピング』で鍛える『思考・判断・表現』と『探究しようとする意欲』」(2024.10/7)では、研究授業(人に見てもらう授業)の回数と自身の授業力は比例すると書きました。https://nakayoh.jp/2024/09/15/
理由は、次の5つです。
1)学習指導要領を読んでから学習指導案を書くので、やろうとしていることが「筋が通っているかどうか」を確認する機会になる。
2)1時間だけでなく、単元全体のつながりの中で、本時がどのような位置付けになるのか、ゴール(育てたい子ども像)に向けてどんな力をつけるための1時間になるのかを考えることができる。
3)やりっぱなしではなく、それぞれの活動を丁寧に振り返り、どう意味付ければ良いかを考えることができる。
4)協議会で質問や助言を受けることで、自分の思い込みや勘違い、または「正しい指導」ではなかった部分に気づけるようになる。
5)授業づくりで大事な視点がわかり、これからの単元計画の見通しが持てるようになる。
いずれも、教師自身の「授業力」向上のためには不可欠な要素となります。「自己内対話」の習慣は、授業の振り返りを言語化したり、マンダラ・チャートなどの思考ツールを使って関連づけたりすることで身についていきます。先に急ぐ授業は「学習者のため」でしょうか。それとも「自分のため」でしょうか。むしろ、教科が好きになる授業、「できた!」と喜ぶ子どもたちの笑顔が生まれる授業になっているかどうかをチェックしてみませんか。