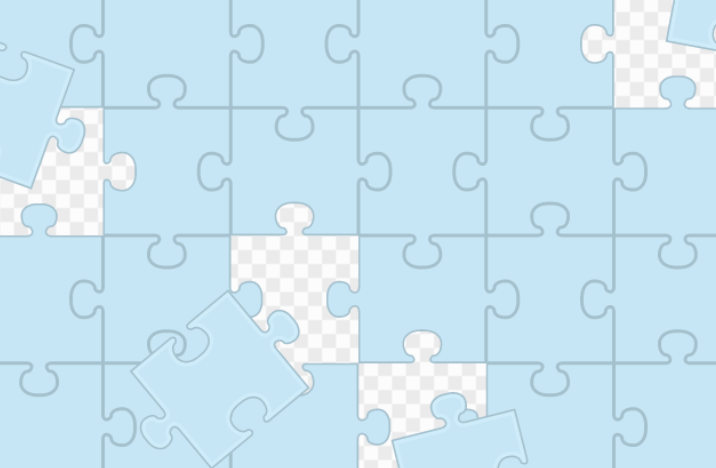創作はジグソーパズルのような営み
私は、「推敲」をしている時間がいちばん楽しく、わくわくします。
完成形を最初から目指すのではなく、まずは“パズルの箱”だけを用意しておきます。そして、そこに次々とピース──思いついた言葉、フレーズ、段落の断片──を放り込んでいきます。とにかく書きたいことをどんどん書いて、あとはそのままにしておきます。いわゆる「原稿を寝かせる」状態にします。
このとき、頭の中では「ツァイガルニク効果(未完了のものほど気になる心理)」が働いて、言葉が静かに熟成を始めます。脳の片隅に“原稿の箱”が残っているので、車の運転中や布団に入ったとき、散歩をしているときに、ふと言葉のピースがひらめくようになります。
まるで、暗闇で光る小さなランプが突然点灯するような感覚です。
ですから、構想は少しでも早く始めるようにしています。寝かせる時間が短ければ、発酵しきらないパンのように、膨らまないままになってしまうからです。
時間を置いて、あらためて“読者の目”で読み返すと、書いた当初には見えなかった粗い部分や不要な表現が、次々と浮かび上がってきます。そんな時こそ、慌てず、ゆっくりと辞書を引いて語義や定義を確かめながら、使いたい表現を丁寧に磨いていきます。この過程は、原石を丹念に研ぎ、光り輝く宝石に変えていくようなものです。
たとえば、2ページの原稿依頼であれば、私はまず6ページ分ほど書きます。そして何回も推敲を繰り返し、不要な部分を削ぎ落とし、最後に2ページにまとめ上げます。
最初1ページしかない(情報が圧倒的に足りないもの)ものを、「足し算」で2ページに仕立てようとすると、パッチワークのようになり、唐突感や不自然さが出てしまいます。
一方、「引き算」で不要なものを判断し、それを順次削っていくと、核心だけが残り、一本筋の通った文章になります。バラバラだったピースが、次第にピタッとはまっていき、やがて最後のピース(画竜点睛)が収まった瞬間──「できた!(つながった!)」という歓びが、全身に広がります。
授業もまた創作──次の1時間こそ”納得できるもの”にする
この“推敲の喜び”は、実は「授業づくり」とよく似ています。
授業もまた創作です。

子どもたちがワクワクする授業にするために、アイデアをメモし、キーワードをノートに書き出し、構成を練る。その工程はまさに、脚本家が舞台の幕開けを準備するのと同じです。
しかも、授業には“完成”(これでよし!)がありません。毎時間がリハーサルであり、本番でもあり、「次はもっと良くできる」と思えることが、教師自身の創造力と主体性を支えてくれます。テストや単元も、次の創作への単なる通過点にすぎません。
私が「授業づくりは、構想と振り返りが命」と言い続けているのは、子どもたちの学びを止めないため、そして彼らが“学びの創作”を楽しめるようにしてほしいからです。
思考ツールは“設計図”──後回しが創造力を殺す
最初から完璧なものにしようと意気込むと、ペンはなかなか動きません。なぜなら、それは設計図を描かないまま、家を建てようとしているようなものだからです。
私は、マンダラ・チャートやマッピングといった「思考ツール」を使って、まず全体像を描きます。それは、創作の“地図”であり、“コンパス”にもなるからです。
この作業をできるだけ早く始めることが、成功の秘訣です。
ですから、「後でやろう」は、創作の敵です。
時間ができる保証などどこにもありません。むしろ、仕事が重なり、「間に合わせるための仕事」になってしまいがちです。そうなると、創作は「楽しいもの」から「苦しいもの」へと変わってしまいます。
そして、いつの間にか挑戦を避けるようになり、さらに「先送り」がクセになっていく。行事の後、延長コードを大急ぎで片付け、「後でやろう」とそのままにしておき、いざ使おうとした時に、コードがこんがらがってしまい、焦り、イライラし、「あの時にちゃんとしておけば」と心から後悔したことはなかったでしょうか。「先送り」したものは、「楽」にならず、逆に後で「苦痛」になってしまうというのが人生です。
だからこそ、一度でいいので、教師は「早めに取り組んで、納得のいくものができた」という成功体験を味わうことが大切です。それが、創作に向かう姿勢を根本から変えてくれます。
授業で「成功体験」を届けよう
教科書も同じです。
文法や語彙を丁寧に教えすぎてしまうあまり、時間がなくなってしまい、新しい文法や語彙の入っていない Project (「思考・判断・表現」の力を高める技能を統合させたタスク)、STEP や Tips(コミュニケーション・スキル)といった、教科書の竹の節(屋台骨)となる「言語活動」のページを飛ばしてしまうという方を見かけます。
しかし、それは「レシピだけ与えて料理は作らない」ようなもの。実際に手を動かし、試してみなければ、「美味しい料理が作れた(英語が実際に使えた)喜び」は味わえません。
各学期に用意された「プロジェクト」の中から、「これならできそう」「ちょっと面白そう」と思えるものを1つ選び、ちょっとだけ頑張って挑戦してみてください。
何でも自分でやらなければと考えてしまうと、負担感しか生まれません。むしろ、子どもたち(グループ)に最初にゴールを知らせ、それに向けてどう頑張るかという「プロジェクト計画書(起案書)」を作らせると、彼らがその気になるので、教師は案外気楽にできます。何より、子どもたちがそれをずっと覚えていてくれます。
プロジェクトをしている間、終わった後の生徒たちの目の輝き、普段とは違う表情や反応に、きっと驚かれるでしょう。また、このような表情が見てみたいと強く思うようになります。
そこから、「技能」を育てるための単元計画づくりへと意識が変わっていきます。
そして、教師自身が得たその成功体験は、授業の中で迷ったときの“方位磁石”になります。
子どもたちも同じです。「できた!」という自信は、練習を重ね、人前で何も見ずに言えたとき、自分でも納得できる成果を出せたとき、そして仲間から温かなフィードバックをもらえたときに、心の奥から芽生えるのです。
そんな「成功体験」の場面を、ぜひ、授業の中でつくってください。
それこそが、教科の枠を超えた──「学級づくり」になるのです。