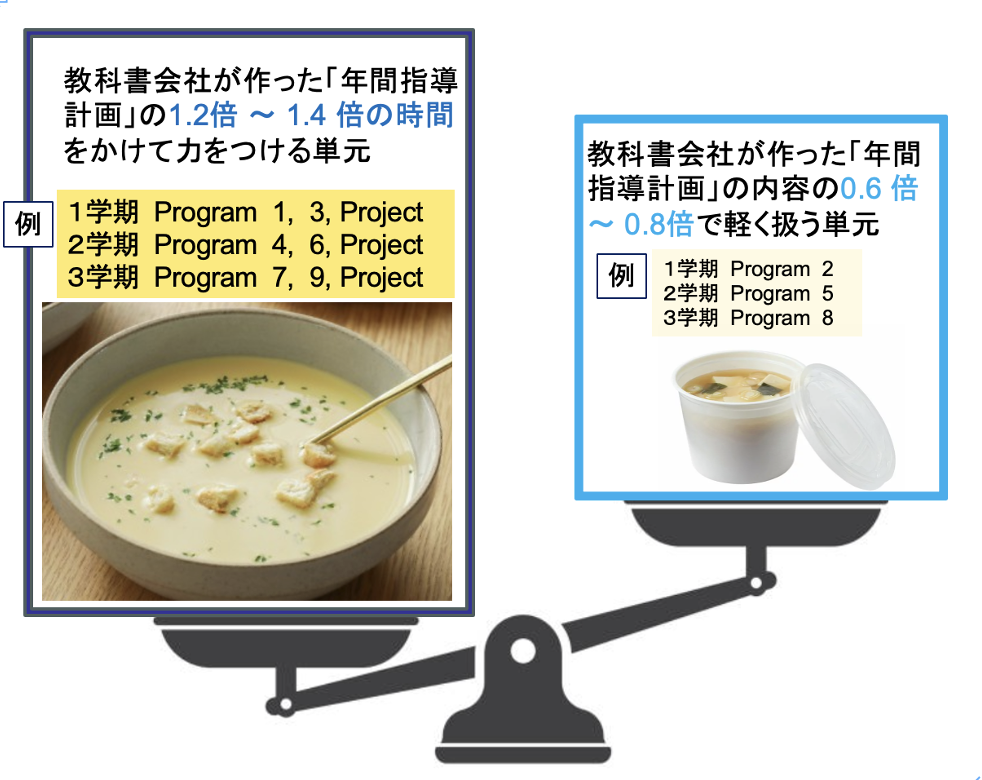◆ その「帯学習」、大丈夫ですか?
以下のような内容の活動を「帯学習」として入れているとしたら、教師が好きなことをする時間と「勘違い」されているかもしれません。
単発の単語小テスト、単元の言語材料とつながっていない英語の歌、クリス・クロスゲームのように一部の学習者しか英語を使わないようなゲーム、シール目当てのお遊びビンゴ、など。
共通するのは、4技能のスキルアップになっていないこと、本時の内容につながっていないこと、さらには帯学習のための「系統的、段階的な指導計画」が作られていないことです。
このようにバラバラなものを、帯学習でいくつも入れているとしたら、大きな時間のロスになります。
「帯」には一定の幅(時間)が必要です。さらに、「帯」は何度も巻いていきます。そのイメージがあれば、帯学習の定義を間違えることはありません。つまり、毎時間同じことをルーティンとして用意するということです。さらに、学習者の様子を見ながら、少しずつ変化を加え(負荷を与え)て、学習者が「できるようになった!」を実感させるようにすること、本時の学習に活かせたという内容にすることが大事です。
4つ(聞く・話す・読む・書く)の「技能」を高めるための指導を「年間指導計画」を立て、帯学習等で系統的、段階的に行っている教師のクラスでは、生徒たちがみるみる話せるようになっています。ノートに書かずにまとまった英文が言えたり、即興でやり取りをしたりできます。
4技能別のスキル・トレーニング・アラカルト(自己診断用)
全ては、「全体計画」次第なのです。ちなみに、皆さんは「4技能」の力を、楽しく、そして確実に高めるためのトレーニングにはどのようなものがあるかご存知でしょうか。
1)「聞く力」を高める指導
① 発音記号通りの正しい発音とストレスの指導(正しく読めないものは聞き取れない)
② Eye shadowing(目だけで追いかける)
③ Prosody shadowing(音だけを拾って追いかける)
④ Content shadowing(意味を考えながら追いかける)
⑤ Silent shadowing (口パクでSynchronized reading)
⑥ Repeating(音源の一文を最後まで聞き取ってから、何も見ないで繰り返す)
⑦ 連結している部分、消失している部分の聞き取り(ディクテーション、英語の歌など)
⑧ Mappingを使ったリスニングのメモの取り方(話される情報をマッピングで表していく)
2)「話す力(発表、やり取り)」を高める指導
① 今までに習った基本文を、全て日本語から英語にパッと直せるための訓練
② small talk(一つのトピックから3文、5文、30秒、60秒と伸ばしていく)
③ ペアでチャット(相手の言ったキーワードを繰り返し、関連する質問を2つする)
④ ペアでインタビュー・マッピング(相手の言ったことをマッピングしながら、深掘りをしていく)
⑤ タブレット端末に自分が話したいものの写真を入れ、電子紙芝居でペアの相手に話す。
3)「読む力」を高める指導
① 瞬時にまとまり(センス・グループ)を理解するために、英語の3つのチャンク(名詞チャンク、動詞チャンク、副詞チャンク)の指導を行う。
② 速読トレーニング(ペンの指し読み。読んでいる単語の2つ前をペンで指しながら動かしていく) ③ チャンクをペンで指しながら、目を速く動かす訓練をする。今までの倍の速さで読めるようになる。
④ どんな英文もつまずかずに(噛まずに)英語らしく読めるようになる build up reading。詳しくは当HP参照。これで指導すると、どんなに英語が苦手な生徒でも、つまずかずに一文を一気に読めるようになる。
⑤ 過去に学んだ単元(すでに意味のわかっているもの)を、語り部になって読む。(音と文字を一致させることで、書く力にも波及する)
⑥ 3人でラジオドラマ作り(声優、ナレーターの役割を分担し、本文を読む。ただし、中にオリジナルの英文を2箇所入れるというルール。BGMも入れる。タブレット端末に録音して提出)
4)「書く力」を高める指導
① 音読筆写(教師が選んだ英文〔7語±1語〕を音読した後、見ないで一気にノートに書く)
② 基本文、新出語彙(発信語彙は全て、受容語彙は自分が使いたいものを選んで)を使って身近な内容のことを取り上げ、3文の文脈のある内容の英文をノートに書く。その中から定期的に良いものを一覧にしてクラス全体で読み、今後の参考にする。
③ 教師が用意した5行くらいのパッセージの間違い探し(時制、綴り、discourse markerなど)をして、全てを正確に書き直す。(×をつけたり、下線を引く程度では力はつかない)
④ 淡白な内容の英文を渡し、どこにdiscourse markersを入れればいいかを考える。
⑤ 自分の書いた英文をノートに書き、生成AIに入れて添削をさせ、修正された英文もノートに写す。その下に自分ができていなかったことを書いて、解説をする。
⑥ 創作スキット作り(できたら演じる)
⑦ 紙上チャット(4人グループで、一人ひとりがそれぞれ発信した紙を時計回りで回し、内容をつなげていく)
⑧ リレー・ノート(グループに1冊。紙上チャットを3分の1に裁断したノートで行う。「正しいやり方」なら、どの生徒も夢中になる。詳細は当HP)
いかがでしょうか。これらは、『英語好きにする授業マネジメント30の技』(2000, 明治図書)でもご紹介していますが、これらを生徒の実態、段階に応じて組み合わせていきます。
私は9年間、3年生を担当していた時に、1学期は徹底してスキル・トレーニングを行い、「聞き取れる・質問できる・高速で読める・ペアやグループで話せる・まとまったことが書ける」生徒を育てようとしました。
教科書の進度は遅れますが、「技能」が高まると、どんどん自分でやるようになっていき、2学期以降は、教科書の内容をあっという間に終わってしまいました。何よりも、「技能」を身につけた生徒たちの学習意欲は、教科書の「知識」を順に教えていた時のそれとは雲泥の差でした。
水泳の練習、自転車の練習、逆上がりの練習と同じで、「技能」は練習をしない限りできるようにはなりません。ですから、技能教科のように、指導方法を組み合わせ、一定期間、継続して練習をするという「計画」がどうしても必要になるのです。
もし、指導者が「無知」である(効果のある指導方法をほとんどご存じなく、ずっとRepeat after me. でやっている)としたらどうなるでしょう。
子どもたちの未来(可能性)がそれによって「縮小」されてしまうかもしれないということです。 また、たとえ教師がそのいくつかを知っていても、授業のプログラムの中に入れて、訓練をする(できるようにする)ことがなければ、自信にはなりません。
教師の仕事は、教えることではなく、できるようにして、自信をつけてやること、指導している教科(英語)を好きにすることです。