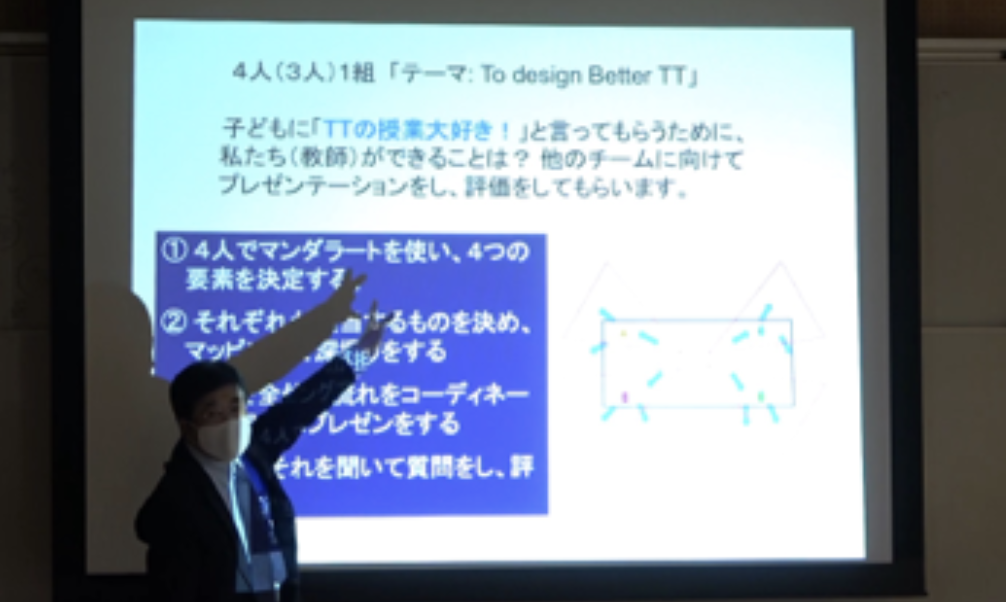◆ 平成型から令和型へ──外見は同じでも動力源が違う
平成最後の学習指導要領と、令和の学習指導要領では、「言語活動」という同じ言葉でも定義やニュアンスが異なります。その変化は、「話す力」を「発表」と「やり取り」に分けた点にも表れています。
結論から言うと、「英語を使っていれば言語活動になる」は大きな勘違いです。
今回の改訂では、「言語活動」(評価対象)と「練習」(評価の対象外)を明確に区別されています。つまり、テキストの音読、Q & A、パタン・プラクティス、ワークシートやタブレット端末(英文が入っている)のような「浮き輪」を使った「練習」(自分の考えが入らない)は、言語活動としてカウントされないということです。
「言語活動」では、オリジナリティ(自分で話す、書く内容を決める)が大前提となります。そこから生まれる「伝えたい、知りたい」が、自然発生するのが「本来のやり取り」になります。やり取りの練習は、あくまでも「練習」であって、問題解決に必要な情報、個々の考えや意見が入らないようなやり取りは、「言語活動」(自然なコミュニケーション)にはならないということです。
以前は、ノートに書いた英文を暗記して発表するだけで、その後のやり取りがほとんど行われない授業も少なくありませんでした。つまり、「言語活動」が本来の「自分の考えを伝え合うコミュニケーション」になっていなかったのです。
今回の学習指導要領の改訂は、「ガソリン車」から「電気自動車」に切り替わったようなものです。
外見は同じでも、動力源と設計思想は大きく変わっています。
もし、この大きな変化を理解せずに、今まで通りで、平成型の「知識偏重」の授業を続けているとしたら、未来からの留学生である子どもたちは、自分で「運転」できる技能を持たないまま社会に出ることになってしまいます。
教師の「意識」(教材観・指導観)は、子どもたちに大きな影響を与えています。
セミナーで、大学1年生の音読(Repeat after me.で育った学生と、発音記号通りの読み方、内容語を強く長く読むことを指導された学生の違い)をご紹介すると、それをご覧になった先生方は一様にショックを受けられます。
前者は「平板な読み」(抑揚もなく、ただ単語を正しく読もうとしている)であり、後者は「語り部」のように読んでいます。しかし、それは紛れもなく、小・中・高の教師によって育てられた姿です。教科書を終わるため、テストのために授業をしていると、前者のような子どもたちが育ってしまうのです。
◆ 「楽しい授業」と「面白い授業」のちがい
短距離走の快感か、山頂からの景色か
感情を表す肯定的な言葉「嬉しい」「楽しい」「面白い」には、それぞれニュアンスの違いがあります。
- 嬉しい … 誰かに何かをしてもらった瞬間の感情(反対語は「悲しい」)
- 楽しい … 嬉しい瞬間が続く満足感(反対語は「苦しい」)
- 面白い … 知的刺激や心の躍動で視界が開ける感覚(反対語は「つまらない」)
授業で大切なのは、漫画やゲームのような一過性の「楽しさ」ではなく、深く心に刻まれる「面白い」体験です。それは短距離走の一瞬の爽快感ではなく、息を切らして登り切った山頂からの景色のようなもの。そこから見える景色は「生きて働く力」(一生覚えていること)になります。
私が、菅 正隆氏、田尻悟郎氏、高橋一幸氏、久保野雅史氏らと、20年にわたって全国を回った「英語教育 ゆかいな仲間たち」の「ゆかいな」とは、「ワクワク感(楽しい+面白い)」のことです。
教師が全てを準備してしまう授業では、この「ワクワクした気持ち」は生まれません。子どもたちが協働し、途中で刺激を受け合い、工夫して課題を乗り越える──そのプロセスの中で、教師もまた彼らと同じ景色を楽しめるようになります。
◆「使わせる」から「使いたくなる」へ
教科書に載っている文法や語彙は、確実に身につけさせる必要があります。だからと言って、教師が頭から教え込んでいたらどうなるでしょう。さらに、肝心の「言語活動」で、教師が「これで話しなさい」「これを使って書きなさい」と条件を課すと、視点は常に教師側に固定されてしまいます。生徒の表情がパッと輝かないのは、ずっと「教科の論理」(教科書中心)で授業が進んでいくからです。彼らが身を乗り出してくるのは、自分の生活経験、既習事項と繋がった時、つまり「生活の論理」(自分たちの実態や興味・関心)が生かされた時です。
学習者が何を話し・何を書きたいかは、学習者自身が決めるものです。だからこそ、「大丈夫、使い方はわかった。今度はそれを使ってみたい。実際に、使えるかどうか試してみたい」と思えるような「心の助走期間」を授業の中で用意する必要があります。
◆ 条件で縛ると“金太郎飴”になる
「早く定着させたい」という焦りから、教師はついお節介(というより、子どもたちにとったら「余計なお世話」)をしてしまいます。
「この単語と文法を必ず使うこと」という条件を細かく設定すると、子どもの表現は似たり寄ったりになります。どこを切ってもほとんど同じ面(内容)です。仲間の文章を読んで「もっと知りたい」と思えないのは、そこにオリジナリティ(新しい情報、具体的で深い内容)がないからです。
生徒に「任せる」と「評価できない」という誤解があるようです。あるセミナーでこんな質問を受けました。
「子どもに任せると、本時で教えたことが使われないのでは?」
パタン・プラクティス、書き換え、間違い探しなどの活動は、言語形式に習熟するためには必要です。しかし、最後の部分まで教師主導でテーマを設定してしまうと、範囲はどうしても狭くなります。
未来表現なら、「明日の予定は?」「週末の予定は?」「夏休みの予定は?」…。
しかし、それは本当に子どもが友だちに知ってほしい(話したい)テーマなのでしょうか?
アンケートをとると、子どもたちはもっと自由で多様なテーマを挙げます。
ドラえもんのアイテムで使ってみたいものと、その理由
過去の時代に行けるなら、どこで何をしたいかと、その理由
こうした「テーマの一覧」を事前に渡しておき、自分で(話す場合はペアで)選ばせます。そして教師はこう伝えます。
「そのお題で、今日(昨日)学んだことがどう使われるか、楽しみにしています」
「教師がさせたいこと」と「子どもがやりたいこと」は一致するとは限りません。だからこそ、テーマを自己決定させ、学習事項をどう組み入れるかを子ども自身が考える課題にするのです。
こうすれば、単元や本時の「評価規準」を見失うことなく、「思考・判断・表現等」の力が自然に育っていきます。
授業は“自分ごと”と“仲間との協働”で満ち、ワクワク感が生まれます。ワクワク感は、教師から与えられるものではなく、自分で決め、自分で取り組むからこそ感じられる喜びです。
◆ 偏らないための心構え
レンズを磨き続ける職人であれ
作家・井上ひさし氏はこう言いました。
むずかしいことを やさしく、やさしいことを ふかく、
ふかいことを ゆかいに、ゆかいなことを まじめに、
まじめなことを だらしなく、だらしないことを まっすぐに、
まっすぐなことを ひかえめに、ひかえめなことを わくわくと、
わくわくすることを さりげなく、さりげないことを はっきりと。
物事は片面からではなく、両面から見ることが大切です。
思い込みは、自分の視界を曇らせます。
確かかどうか、辞書で定義を確かめ、情報の出所もきちんと確認する──
子どもたちが真摯に取り組もうとする授業を「また聞き」や「伝言ゲーム」で進めないために ーー
教師は常に「レンズ(自分の視点)を磨き続ける職人」でありたいですね。