🌱 参加者からの事前質問(答え)
事前に川越の研修に参加される方から、次のような質問をいただいていました。簡単なコメント(質問に対する答え)を載せておきます。関心のある方はお読みください。
⑴ 校内の研究授業のために、先月、令和型学習指導案を見よう見真似で作成しました。しかし、やはり「我流」で作成したものであり、それが本当に機能しているのかどうかわかりません。令和型学習指導案を作成するにあたり、段階を追って、まずどこから手をつけていけばよいのか、教えていただけたら幸いです。
◆ 順序は次のとおりです。当HPで紹介されているものを参考にしてください。検索に「令和型学習指導案」といれていただければ、ジャンプします。
1)学期の最後に位置付けられている「プロジェクト学習」(「知識及び技能」、「思考・判断・表現」を総合的に評価する統合型タスク)で身につけておかなければならない「技能」(4技能別)をマンダラ・チャートで洗い出す。
2) それを元に、学期のそれぞれの単元で、何をどこまで身につけるのかを、新しいマンダラ・チャートで考える。(細分化し、具現化していく)
3) 令和型学習指導案(育った生徒の姿から逆算をして単元全体を計画する)を作る。
① 必要な時間数の数だけトランプ大のカードを用意する(たとえば6時間扱いとするなら6枚用意する)
② 6枚目(最後の6時間目)のカードから書き始める。最後に何がどれだけできるようになっていなければならないか、その育った姿を具体的に書く。それが最後の時間でどう評価されるのか、評価内容と評価方法を書く。
③ 次の5枚目のカードを取り出し、6枚目のカードに繋げるには、何を指導しておかなければならないかを書く。6枚がつながったストーリーになるように、順に4枚目、3枚目、2枚目、最初のカードというように書いていく。
④ 6枚の順番が最終的に決まったら、今度はカードを裏返し、子どもたちが主体となって活動する言語活動、そして教師・生徒/ ALT・生徒 / 生徒・生徒のインタラクションの場面を考える。
⑤ カードの裏に書いたことがつながったと思ったら、最終的に3色付箋(Post-it)を用意し、教師主導の活動にはピンク色、個人の活動には黄色、ペアやグループのように関わりのある活動には緑色の付箋を貼る。同じ色が繋がっていないか、緑の前は黄色になっているか、緑の後にピンクが来ているかを確認する。
研究授業の機会は滅多にありません。そこで、単元をひとまとまりのつながりが生まれるように丁寧に単元全体の計画を立てます。大事なのは、一度でいいから「成功体験」をすること、そのイメージを作ることです。すると、指導案を書かなくても自然にできるようになります。
⑵ 以前の講演で、セサミストリートやオックスフォードの写真付き辞書を引き合いに、英単語を英語で、そして文脈で理解する大切さを教えていただきました。私も何度か、授業で真似してみました。スライドに単語に関連した写真と、単語を英語で説明した簡単な文章を載せ、全体で共有しながら確認しました。しかし、私のやり方だと英単語を英語で理解する必然性がないからなのか、もしくは、すぐに日本語で答えを与えてしまうからなのか、英語で意味を推測しようという気持ちがなくなるからなのか、あまりうまくいっていません。新しい単語を導入する際、効果的な方法があれば、ぜひ教えていただきたいです。
◆ 英英辞典に書かれている定義をそのまま使って教えるのではなく、あくまでもそれを参考に、子どもたちの実態に応じてさらにわかりやすく rephrase することが大事です。忘れてはならないのは、for instance で具体例を示すことです。ただ、私の場合はそれをクイズ形式にしてマスキングを使い、キーワードを4択で選ばせていました。その形式を定期テストの単語の問題として出していました(同じ問題は出さない)。テストにつなげない限り、生徒は必要感を持たないのでやろうとはしません。
⑶ 生徒にたくさん話させようと思ってもすぐに日本語が出てきてしまいます。こちらが英語で質問しても、日本語で返ってきたり、こちらが英語で言い直しをしても、次の生徒を指名するとその生徒もやはり日本語で答えてしまいます。英語の発言を引き出すにはどうしたらよいでしょうか。生徒の話したいことを結局こちらが 勝手に英語にして話しているだけの状態になってしまい、モヤモヤしています。
◆ 帯学習で「picture describing」の活動(ペアの一人が提示された写真やイラストを英語で説明する。相手は目を閉じてその説明を聞き、それが何かを当てる)を用意することです。教師からの「文法の使い方」(language usage)の説明だけではできるようにはなりません。楽しくできる言語活動(language use)こそがポイントになります。
⑷ 中嶋先生のご著書を読ませていただいた際に、毎学期、教師の通知表をつけてもらっているという記述がありました。授業について、どのような項目を生徒たちに評価してもらっていたのか教えていただきたいです。今回の講演の内容とは異なりますが、可能でしたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
◆ 次の項目を用意し、それぞれ5段階でつけてもらいました。(できていた→5)
1) 外部試験や実力テスト(定期テスト以外)で成果はありましたか。
2) 授業は、概ね、楽しく受けられましたか。
3) (4技能で)自分ができるようになりたい技能は伸びましたか。
4) 仲間と協力し合える、居心地の良いクラスになっていたと思いますか。
5) 教師は、やるべきことをきちんとやっていたと思いますか。ひいきや差別はありませんでしたか。
さらに、次のことを聞きました。
⚫︎ 特に印象に残った学習(単元)は何でしたか。それは何故ですか。
⚫︎ 力がついたと思う活動はどれですか。それは何故ですか。
⚫︎ あまり面白くなかった活動(単元)はどれでしたか。それは何故ですか。
⚫︎ あまり効果がなかったと思う活動は何でしたか。それは何故ですか。
⑸ 小学校英語の課題は、「中・高校で経験のある)外国語専科教師」か、それとも「元々小学校で教えていた先生」なのかによって決まると思っています。つまり Time on Task で「教科書をアレンジ」できるプロなのか。あるいは教科書を「網羅的に教える事のみが仕事」だと勘違いしている先生なのか。授業スタイルは自ずと大きく異なってまいります。コレは行政なり文科省なりがきちんと施策を打ち出せていないことに起因するものと思われますが、一体どうしたら良いのでしょうか?
◆「言語活動を通して」を正しく理解できていることがポイントになると考えます。専科であろうが、担任であろうが、それを具現化できるかどうかです。さらに、原因や理由を文科省や行政に求めるのではなく、ご自分で「何が大事か」を理解し、仲間(同志)を増やすことをお勧めします。「英語教育 ゆかいな仲間たち」は、菅 正隆氏(大阪城南女子短大 学長兼教授)と一緒に「現場の先生を元気づけよう」「子どもたちが主体となる授業を目指そう」と考え、田尻悟郎氏(関西大学)、高橋一幸氏(神奈川大学教授)、久保野雅史氏(神奈川大学)に協力をお願いし、20年間で全国を回りました。全員が大学で教えるようにはなりましたが、指導主事や教員のときにそれを立ち上げ、アクションを起こしました。教師の仕事は授業だけでなく、ヒューマン・ネットワークをどう構築し、それでどんな具体的なアクションが起こせるかということも大事なことのように思います。決して難しいことではありません。仲間(同志)と出会うには、学校外に出ることです。
⑹ 生徒が積極的に歌えるような英語の歌の指導法や、選曲のポイントについてアドバイスをいただけますと幸いです。
◆『”英語の歌”で英語好きにするハヤ技30』(単著・明治図書出版)と『決定版!授業で使える英語の歌20(正続)』(北原・田尻・久保野らとの共著・開隆堂)が参考になるかと思います。前者は、中学校3年間の「歌の年間指導計画」を紹介しており、さらに「歌の指導を通して表現力を豊かにする実践」なども見られます。後者は、6人の「知恵」(読み取り、聞き取り、訳詞家になろう、好きなフレーズを使ったスピーチなど)がふんだんに紹介されています。ぜひ、参考になさってみてください。ただ、すでに絶版になっているものもありますので、その場合は、どなたかお知り合いの方(お持ちの方)に見せていただいてください。
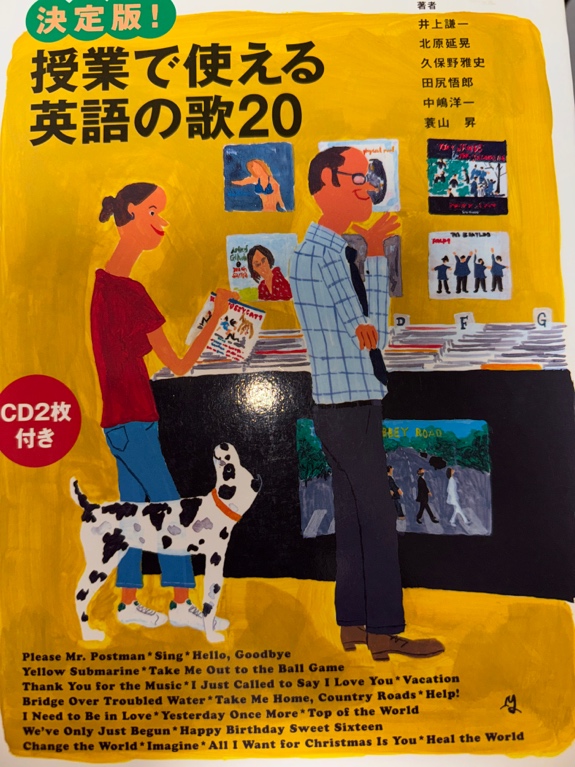
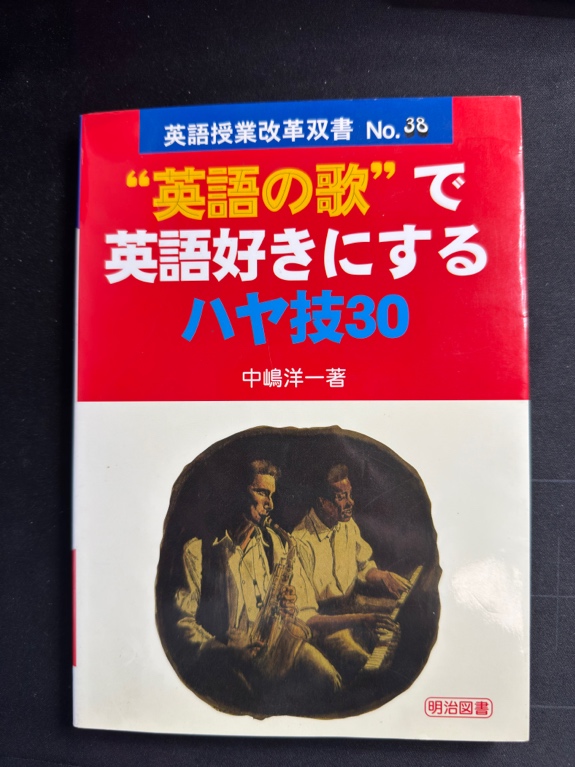
P.S.
次は8月後半の予定です。これについては9月に入ってからいくつか内容をご紹介したいと思います。
8月19日(火)神戸市小中外国語教員研修
8月25日(月)神奈川県 県央小中合同研修会(直山氏とのジョイント)
8月28日(木)滋賀・大津市教員研修
8月29日(金)富山・小矢部市の中学生600名対象のキャリア教育講演
「ありがとうが増える学校」
8月29日(金)県民カレッジ 高岡地区・教養講座
「オンリーコネクト(すべてはつながっている)」







