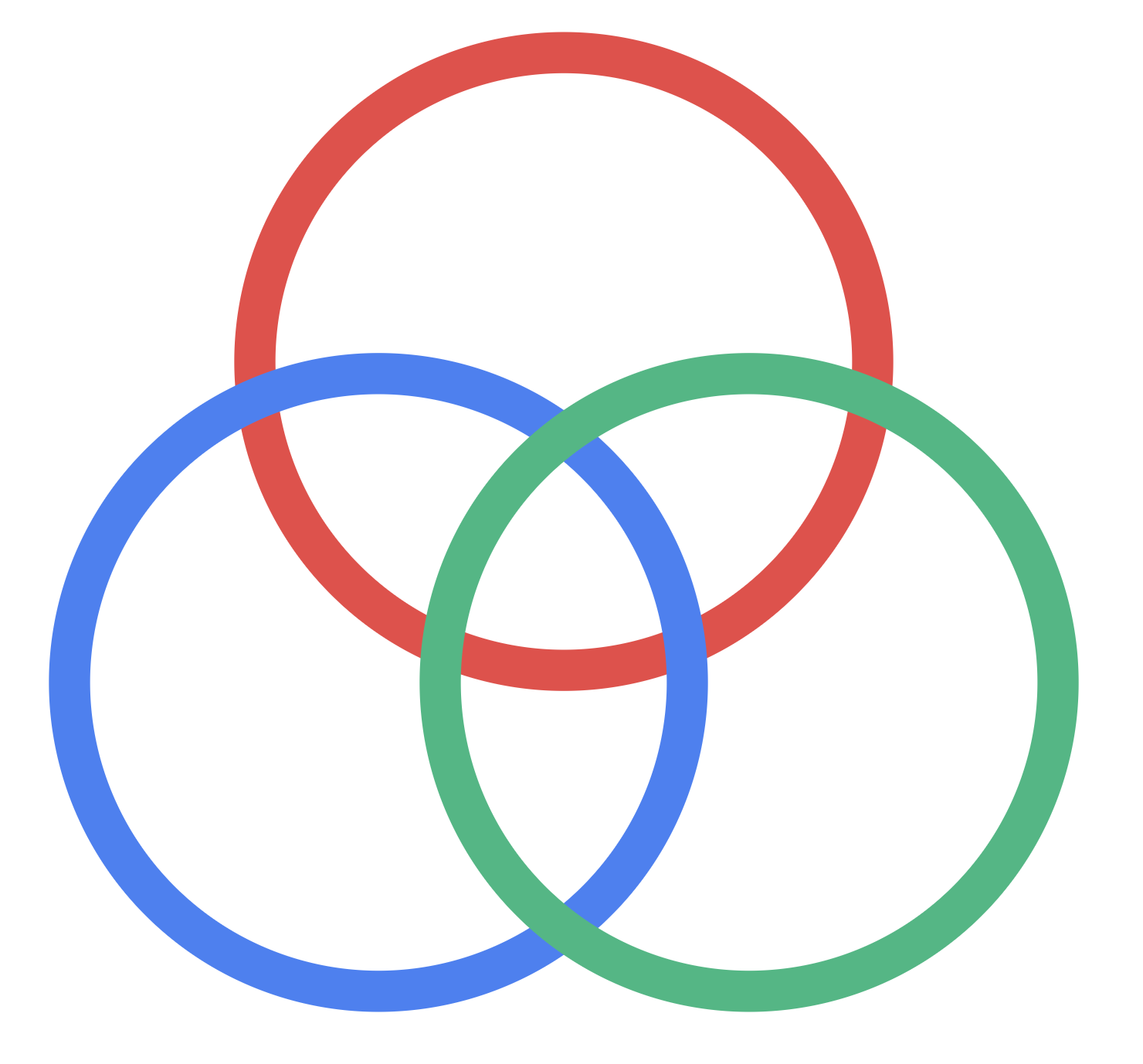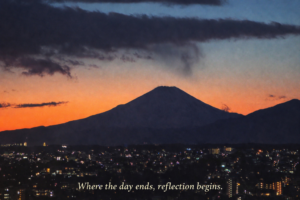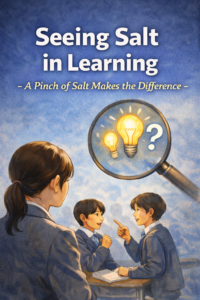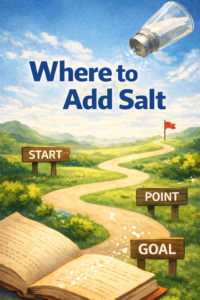🪞 なぜ、吸い込まれてしまうのか
「中嶋先生のお話は吸い込まれてしまいます。どのように訓練されたのですか?」
よくそのようなことを聞かれます。そんなとき、私は「次の3つを大切にしています」と答えています。
⚫︎ 胸の奥から湧き出る言葉で語ること。
内容が浅かったり、納得できるものでなかったりしたら、どんなに表情豊かに話しても心には響きません。大事なのは、胸の奥から出てくる言葉、事実です。
⚫︎ 聞き手がイメージできる比喩や具体例を盛り込むこと。
言葉が絵や映像に変わったとき、話された内容は心に残ります。
⚫︎ 表情・間・抑揚を意識すること。
楽器に例えるなら、言葉とは旋律、間は休止符、表情は楽器の音色であり、人の心に残るのはそれらが「三位一体」となったときです。
教師は、教える前に、目で、表情で、声で相手を惹きつけられなければなりません。思わず、話を聞きたくなる雰囲気を持っていることに、私たちはより心を砕かなければなりません。
荒れた学校を3校、経験したことから、それを痛切に感じます。
授業で学級づくりをすること、授業の中で本当の「生徒指導」(自己実現)を行うことで、居心地の良いクラスになります。日々、自分の成長が実感できるようになります。教科書を先に進める授業ではそれができません。
🪞 “鏡”が語りかけたもの
学校が荒れていた頃、M校長先生は各階の踊り場に等身大の鏡を設置しました。教師からは「壊されるのでは?」「もっと使い道があるのでは?」と不満も出ました。
しかし校長先生は毅然とこう言われました。
「鏡は自分の心を映す。授業に入る前に、笑顔の自分を映してから子どもたちの前に立ってほしい」
洗面所の鏡は顔だけを映します。すると、どうしても顔や頭髪といった部分だけを見てしまいます。
しかし、等身大の鏡は“教壇に立っている自分””生徒が見ている自分“を映し出します。そこに映っているのは、威圧する表情ではなく、生徒が安心して話を聴こうとする教師でなければなりません。
校長先生は、大人側が用意した「規律」ではなく、「授業のワクワク感」(学習への飢餓感、知的興奮)こそが最大の指導だと示してくださったのです。
🪞 怪談という魔法の呪文
以前も、このHPで「怪談」のことをご紹介しました。それは、自分の教師としての「土台」を作ったと言っても過言ではないからです。
荒れていた時、私は生徒が「怖い話好き」だと知り、怪談集を買い込み、語り部のように練習しました。
怪談は、ただの怖い話ではなく、”空気”を変える魔法の呪文になるのです。
声の抑揚、沈黙の間、ちょっとした身振り──それらが重なった時、ゾクゾクッとする“体験”が生まれます。「お前だーっ」のタイミングがズレたら、すべてが台無しになります。
ある日、私は、廊下にたむろする生徒たちに「怖い話をするから教室に入りなさい」と誘いました。練習を重ねた怪談を披露すると、教室は「きゃーっ」「ひーっ」と悲鳴が起き、その後笑いに包まれました。
翌日から彼らは自ら教室に入り、「カイダン!カイダン!」と合唱し始めました。私はそれを制してこう言いました。
「楽しいことは後で。まず授業を頑張ろう」
この“後に楽しみを置く”手法は、学習意欲を持続させる大切な仕掛けです。
英語の歌も授業の最後に歌うと、終わりのチャイムが鳴っても余韻が広がり、子どもたちの記憶に「英語の授業は心地よい時間」と刻まれます。
◆ 利己から利他へ──変わる教師の視点
授業で寝てしまう生徒に「起きろ!」と叱りつけるのは簡単です。
しかし、不思議なことに、私は「これは自分の責任だな」と思いました。
怪談を楽しみに授業に参加するうち、生徒たちは私語をやめ、静かに耳を傾けるようになり、こう言いました。「中嶋先生の授業、怪談みたいに吸い込まれる」
その時、私は気づいたのです。
自分の“教えたいこと”ではなく、相手が“聞きたいこと”に寄り添っていたということを。
話し方は「利己」から「利他」に変わり、教材は“相手目線”で生まれていく──。
それが彼らの「学び」を生き生きとさせるのだと。
そのためには、より理解しやすい、イメージしやすい言葉であり、想像しやすいシーンを頭に描かせることです。そこで、できるだけ「たとえば」で示す例、「ちょうどーのようなもの」のようなメタファーを使うようにします。このHPでも、それを意識しているつもりです。
◆ 吉本に学ぶプレゼン力
この話も2回目です。以前、🟠「働き方改革」の迷走も「TT」の混乱も根っこは同じの記事の「ALTとのTTは何のためなのか(ゴールを共有しているか)」でも、吉本の寄席に行って行なったセミの研修について書いています。繰り返しになりますが、違う視点から書いてみます。
実は、高知に研修で呼ばれたとき、その学校の校長先生(美術)は、「教師は吉本から学ぶべきだ」という考えをお持ちで、毎年の職員旅行を難波花月にしておられました。私もゼミ生を京橋花月に連れて行っていたので、意気投合しました。
私が、ゼミ生に課したレポートは「私が吉本の芸人から学んだ3つのコミュニケーション能力」でした。ゼミ生たちは、普段は笑いながら楽しんでいるであろう漫才や落語を、メモをしながら芸人たちを追いかけていました。それをみた他の客は、きっと不思議に思われたことでしょう。
やがて、寄席が終わり、ゼミ生たちは、次のようなことをレポートしてきました。
⚫︎ 芸人が登場した瞬間に会場が明るくなることの意味。
(スポットライトが当たるのはお客さん。お客さんの様子をみながら芸を見せる)
⚫︎ ネタが滑った時のリカバリー術。
(客席から声がかかることもある。予定調和ではなく、臨機応変に対応する)
⚫︎ オチまで自然に導くタイムマネジメント。
(抜群の間の取り方、阿吽の呼吸があってこそ「笑い」が生まれる)
いずれのレポートも、これらのことは「教師が日々行う授業」に不可欠な要素ではないか、ネタを研究し、話術を磨くことは、単に単元を教えるための「教材研究」レベルのことではないということを述べていました。
寄席には、お金を払って足を運んでくれる客がいます。一方で、毎日、つまらなくても授業に出てくれる子どもたちもいます。彼らは、どちらも当たり前ではないと考えました。
漫才を8割“楽しみ”、2割“観察”する──その訓練がプレゼン力を磨きます。
クイズ番組の視聴でもそうです。フリップの作り方、出し方、そしてCMに入る前にどこで切るか(ツァイガルニク効果)などです。
教師もまた、話しながら自分を俯瞰する「二重の視点」を持つことで、授業の質が変わります。
◆ 航海士としての教師
講演や校内研修の講師をやりながら、よく考えることがあります。
教師とは、未知の海を進む航海士だということです。
ときに鏡で自分を映し、怪談の呪文で心を開き、芸人から間と笑いを学ぶ。
そうした体験のひとつひとつが、授業という航路を描く羅針盤になるのです。
今、新刊執筆に挑んでいる6人の「航海士」たちから、マンダラチャートやマッピングで練り上げた構想が届いています。
そこには、私が冒頭に掲げた3つ──胸から出る言葉、比喩と具体、表情と間──が息づいており、思わず読みたくなってしまいます。