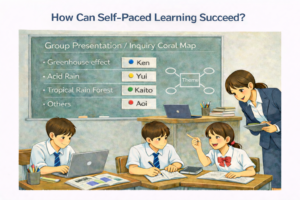💠 割れ窓理論とは
「割れ窓理論」とは、1枚の割れたガラスを放置すると、次々にガラスが割られていくという、政治学者ジェームズ・Q・ウィルソンと犯罪学者ジョージ・L・ケリングが1982年に提唱した考えです。
荒れた状態をそのままにしておくと、「誰も気にしない」「誰も責任を取らない」という気持ちになり、やがて「無関心」の空気が蔓延してしまうのです。
1990年代、ニューヨークのジュリアーニ市長は、軽犯罪や秩序維持を徹底するために、治安改善を進めました。本気で取り組んだのが地下鉄の落書き一掃です。それは1980年代後半、デヴィッド・ガン総裁が主導した取り組みで大きく進み、その後も秩序維持策が継続しました。これらの積み重ねが美観と体感治安の改善に寄与した、と評価されています。
同じ仕組みは、ディズニーランドやシンガポールにも見られます。
ディズニーは「14歩ごとにゴミ箱」と言われるほど清掃を徹底し、常に美観を保つことで、来園者の行動意識を変えています。
シンガポールでは、ポイ捨てに対して初犯で最高1,000シンガポールドル、再犯ではさらに高額の罰金が科され、加えて公共清掃の社会奉仕活動も課されます。その結果、環境が美しく保たれ、それがさらに観光客を引き寄せることにつながっています。
人は、整然とした場所にゴミを捨てようという気持ちにはなりません。トイレが綺麗に管理されている場合も、知らず知らずのうちに「ルールを守らなければ」という気持ちになります。
観光地、高速道路にあるSAやPAなどで、海外からの観光客が日本の公衆トイレが綺麗なことに驚くのも無理はありません。
💠 教育現場に引き寄せると
学校もまた「割れ窓理論」と無縁ではありません。
掲示物が破れているのを放置する、提出物の遅れを見逃す、授業中の私語を黙認する――こうした「小さなほころび」は、「本気にならなくてもいい」という空気を作ってしまいます。
「わからない」ことが常態化し、「別に、できなくてもいいや」と思ってしまうと、やがて無責任な行動が増え、授業が停滞し、気持ちは荒れていきます。
反対に、教師が黒板をきれいに使い、生徒のノートを丁寧に見て、提出物の期限を守らせる。そんな「確かな秩序」が積み重なると、教室の空気はみるみる変わっていきます。
「授業は楽しいし、力がつく」 「この先生は信頼できる」 「仲間との協働学習では新しく気づくことが多い」 ―そうした雰囲気が当たり前になっていけば、同時に学力も向上していきます。
必要なのは、互いを尊重し合い、助け合う経験です。授業、生徒会、学校行事 ― その中で子どもたちは挑戦し、失敗や挫折を乗り越え、成長していきます。
教師が心がけることは、「失敗させない指導」ではなく、「気づき(自分なりの教訓)」を得るには、失敗や挫折は当たり前と考え、それを乗り越える中で「自分の学び」とさせることです。
「上手くいったかどうか」「勝ったか負けたか」といった表面的な振り返りではなく、自分が成長をするために、「自己更新」をするために「何を学んだのか」「何を次回に活かすのか」という視点で振り返ることを徹底することです。
教師が、教室の学習環境や掲示物などに無頓着であれば、子どもたちの心が豊かに耕されることはありません。教師の意図的な仕掛けによって、学習者が「ハッと気づける」ようになっているか、一人ひとりの成長を喜びあえるような学級経営ができているかどうかは、授業以前の問題です。
また、授業においては、自己流(今までどおり)ではなく、「正しい指導」によって「できた!」という実感を積み重ねられるプロセスになっているかどうか。これも学習環境に含まれます。
💠 「失敗させない教育」ではなく「失敗から学ぶ教育」
冒頭でも言いましたが、もっとも怖いのは「無関心」です。
「できなくてもいいや」と思う子どもが増えると、やがて教室全体に停滞感が広がります。
大切なのは、互いを尊重し合い、トライ&エラーズ(とにかく挑戦すること)を当たり前にしてしまうことです。授業、生徒会、学校行事――子どもたちはその中で失敗を経験し、挫折を乗り越えて成長していきます。
教師の役割は「失敗を未然に防ぐ」ことではなく、「挫折」や「失敗」をおおらかに受け止め、それを学びに変えるプロセスを大切にすることです。
掃除や後片付けも同じです。
「やりなさい」と指示するだけでは何も変わりません。
必要感や使命感をどう作るかです。
所属感を高める指導をすれば、「みんなのためにやろう」と考えるし、活動の最後に成就感を振り返るようにすれば「きれいにすると気持ちいい」と子どもたちは考えるようになります。行為をどう意味(価値)づけるか ― それこそが教師の腕の見せどころです。
まとめ
割れ窓理論が示すのは、「小さなほころびは、やがて全体の空気を決めてしまう」ということです。 教師も、それを警句としなければなりません。
もし、教師が「前兆」に気づかなければ、あっという間に広がります。
教師の仕事は、クラス全体に「正しい指導」を求める空気を醸成することです。教師からの押し付けでもなく、結果だけを評価するような窮屈な指導でもなく、子どもたちが「こんなクラスで学びたい」という願いを叶えることです。
学校は、子どもたちが失敗を恐れず、問題を発見したら自分の頭で考えて解決をしていく、途中いつでも自己調整することを当たり前にする習慣を身につける場です。
そのために、教師は、現状や実態を丁寧に把握し、居心地の良い「秩序」を少しずつ積み上げていくことを目指します。それこそが、子どもたちの未来を明るくする最も確かな道であるように思います。