生徒が納得するのは「目的」(何のため)のあること
TTの授業を拝見させていただくと、「自分の町のことを伝えよう」「自分の好きなことを伝えよう」「ALTに自分たちのことを紹介しよう」「ALTに日本のPop Cultureについて説明しよう」といった課題が多く登場します。それが「当たり前」になっているようです。
しかし、これらは教科書で学んでいる文法を使った「練習」、または教師が考えた課題に過ぎず、生徒は「必然性」を感じていません。中には、「必然性」を勘違いしている方もいます。とにかくALTが出てこないと「英語を使う必然性がない」という思い込みから「ALTの友人が今南極にいます。南極は今、地球温暖化でいろんなことが起きています。友人からALTにそれを知らせるメールが届きました」のような設定(実際は架空の話)を無理矢理作った研究授業もありました。参観していたALTたちが “What? What for?” と言って首を傾げていました。
このような「習った文法を使わせたい」という教師の思惑いっぱいの課題をよく見かけます。あちこちで「なんで?」「その後どうすんの?」という生徒のつぶやきが聞こえてきます。しかし、概ね、やらされることに対しては成績も絡むので、仕方なく忖度するようになります。
最初に、「何のために町のことを教えるのか?」「自分の好きなことや自分たちのことを教えたら、ALTはその後どうするのか?」「ALTは日本のどんな Pop Culture に興味があるのか?それは何故か」といった疑問をクリアーしてやらないと「自分ごと」にはなりません。しかし、一旦「自分ごと」になった課題からは、学習者の「知りたい」「伝えたい」が生まれてきます。
まず、「何のためにするのか」という「目的」を知らせることです。肝心な「ALTがそれを知ってどうしたいのか」「知った情報を使って何をしたいのか」が示されていないです。しかも、これらの課題を日本人教師が指示しているところがNGです。ALTが知りたいのであれば、ALT自身から「何のためにその情報が欲しいのか」を自分のメッセージとして伝えなければなりません。ALTが授業に出られないのなら、3分程度のビデオレターでも構いません。
(参考 「なぜ、TTがうまく行かないのか」(治療編 3/3の福岡市立城香中学校2年の授業)
それを受けて、日本人教師は生徒にこう聞きます。「みんな、事前に何を知っておきたい?」「ALTへの質問時間をとります」。これは「場面」と「状況」を明確にするためです。こうすると、生徒は「日本のどんなPop Cultureに関心があるのか」を聞いたり、「今までどこに行ったのか」と尋ねたりするでしょう。
「自分のことを伝えよう」ではなく、ALTから「英語の授業を面白くしたいので、みんなの興味関心についてもっと知りたい」と生徒に伝えると、生徒は具体的に好きなジャンルの音楽や歌手の情報を取り上げたり、好きなゲームの内容などを伝えようとしたりするでしょう。
ALTが「私が日本のPop Cultureで関心のあるのは5つです。それぞれ、そのことについてもっと詳しく教えて欲しいです。4人(3人)のチームで2分のプレゼンテーションをしてください。『へえー、そうなんだ』と大いに納得できたら『いいね!』がもらえます。チームで、いくつ『いいね!』がもらえるか、みんな頑張って」と言います。JTLはプレゼンテーションの評価について説明します。チームの得点は5点満点、個人が5点満点、合計で10点であること伝えます。
こうすると、苦手な生徒もチームのために一生懸命に取り組むようになり、他の生徒たちもワンチームとしてサポートするようになります。
有効なのが「探究コーラル・マップ」を使うことです。最初に、自分たちが選んだテーマ(ALTの関心があるPop Culture)から、マンダラ・チャートを使い、4つの要素(歴史について、アハ情報、できること、身近に経験できる場所など)を自分たちで選びます。さらに、一人ひとりが責任を持って担当をする内容を決め、その後「階層式マッピング」で深掘りをしていきます。最後は、全員が作成したスライドを繋いで、原稿を書かずに写真を見せながら Show and Tellをする練習をします。他のチームに見せて、わかりにくい部分へのアドバイスももらいます。こうすると、個別最適な学び(個人の関心、習熟度など)と協働的な学び(刺激、peer learning)が融合され、往還してきます。
次にご紹介するのは、単元最後の活動(タスク)が「ALTの先生に日本語で書かれた本を紹介しよう」になっている授業です。単元の計画は次のような展開です。
第一次
◆司書の先生から本紹介の手順を学ぶ。
・本の基本情報(作者、タイトル、あらすじ)を整理する。
・事実だけではなく、紹介したいセリフや表現を書き出し、自分の思いを付け加える。
第二次
◆ALTの本紹介を聞いて、自身の本紹介に取り入れることができる表現を発見する。ALTからのお願い(日本の本で日本語を学びたい)を理解する。最後にALTに向けてプレゼンをすることを知る。
教科書に載っている活動を参考に、習った言語材料を使ってプレゼンテーションをするという指導のようです。ただ、生徒はいきなり司書の方から「本の紹介」の手順を説明されても、「なぜ英語でそれをするのか」がわからないでしょう。では、順序を逆にしてみます。まず、登場するのはALTです。(最初の授業に出られない場合は、Short Video Letter(2分程度)を用意してもらいます)
まず、ALTが「今、日本語を勉強している。日本語は難しいけど、勉強は楽しい」と語り、読んでいる本を実際に見せます。そして、「絵本が好きで、今までこんな本を読んだ。こんなことを勉強した。少し日本語がわかるようになった。みんなの知っている本で、もっといい本があったら教えてほしい」と伝えます。さらに「どこまで日本語の文字(ひらがな、カタカナ、漢字のレベル)が読めるのか」、そして「好きなジャンルは何か」といった情報も与えておきます。
この場合、言語活動の「目的」は「いろんな絵本を読んで日本語がもっと上手になりたいと望んでいるALTに対して英語でアドバイスをすること」です。「場面」や「状況」としては、「どんな本を選べばいいのか」、「どういう点でそれが役に立つのか」を説明できるか、そして「具体的な発表の仕方や評価の仕方」はどうなっているのかといったことが頭にイメージできるようにすることです。
評価については、ALTにとって本当に役に立つ提案であったかどうかを「評価項目」に入れなければなりません。その点数がもっとも大きくなります。つまり、内容です。次に来るのが、分かりやすさ、英語らしさ、プレゼンテーションの工夫、などです。ALTと日本人教師が評価をします。生徒は直接評価をしなくても、ALTがなぜそれを選んだのかを考える「振り返り」の時間を用意します。教師が、アイコンタクトやジェスチャーを観点に入れてしまうと、そこ(ポイントをもらうこと)に関心が向かい、そこだけを大げさにやろうとする生徒が出てきてしまう危険性があります。
ポイントは、それぞれの授業に「のりしろ」を用意することです。毎時間、やろうとしていることが単元最後のゴールである言語活動(タスク)と「のりしろ」があるかどうかをチェックすることです。
1時間ごとの授業(ワン・ピース)をジグソーパズルのように組み合わせていくのです。そして、HPの記事「なぜ、TTがうまく行かないのか」(治療編 2/3)の3人の学習指導案をご覧いただければわかると思いますが、網掛けの部分(「前時とののりしろ」と「次時へののりしろ」)を丁寧に記しておくことです。こうすると「教えなければならない」「終わらなければならない」といった窮屈な思いではなく、習ったことをどうつなげればいいか、どう「言語活動」に活かせばいいかを考えられるようになります。生徒が教師に指示されたこと、その答えをやり取りする活動ではなく、あくまでも生徒がどう思ったか、どちらを選んだか、そしてそれは何故かという根拠や考え(意見)を交流させるのが「言語活動」であり、その質を高次のレベルに高めることが教師の責務です。
小手先の指導(導入で引きつける活動を用意する、ゲームを入れる、文法のプリントを用意する、など)ではなく、今、取り組もうとしていることが果たして学習者の「内発的動機付け」(intrinsic motivation)につながるのか、「必然性+わくわく感」から「やる気スイッチ」がオンになるのかを最初に丁寧に考えておくことです。
ノートやワークシートに英文を書いてしまうと、それをそのまま読もうとする、またはそのまま暗記しようとする生徒が育ちます。日頃から「書くのは最後のステージ」ということをルールにしてしまうことです。それまでは「メモ」(名詞)のみにします。マンダラ・チャートやマッピングで「名詞」だけを書くのがルールになっているのは、名詞(キーワード)を繋いで英文を組み立てられる力をつけるためであり、それが「即興性」の土台になるからです。即興で話せないのは、そのような指導をしないで、ノートに英文を書くという「正しくない指導」を行なっているからです。文科省は、メモ(キーワードとなる名詞)をもとにやり取りをし、最後に情報を整理するために書くことを奨励し、言語活動に入る前に、予め内容(英文)を用意してしまうこと(やり取りの必然性がなくなる)に警鐘を鳴らしています。
Backward designや「令和型学習指導案」とは、単に逆向きに授業(1時間のコマ)を並べ変えることではありません。上に書いたように、単元の学習全体に「筋」を通し、明確な「目的」(何のために、何ができるようになるのか)が考えられるようになることです。そのことによって、学習者にとって英語を使う「必然性」(相手が英語を話すこと)や学習の「必要感」(学習が「自分ごと」になり、「なるほど、それならこうしたい」と考えられる)が生まれるような授業デザインができるようになるのです。
「練習」の活動は単発で終わり、「言語活動」は技能がリンクしていく
TTで望ましいのは、ALTと一緒に単元全体のどこにどんな「言語活動」を入れれば良いかを考えることです。
TTの授業(1時間)をどう進めるかという場当たり的な取り組みでは、授業の質は高まりません。かなり早い段階(できれば春休み、夏休み、冬休みなど)で、先の見通しを持って単元でつけたい力とそのレベル(4技能)を話し合っておきます。必要なのは、学習指導要領を読み込んで、つけなければならない力だと思う箇所に下線を引き、それを授業でどう計画的、系統的に身につけていくのかをALTと一緒に話し合うことです。それをしてから教科書を見ると、教科書に載っているタスクが「何のためなのか」がわかるようになります。すると、「教科書に載っているからやらなければならない」といった受け身の発想から、「最後の統合的なタスク(Stage Activity_New Horizon, Project_One World/New Crown/Blue Sky, You Can Do It_Here We Go, Our project_Sunshine English Course など)で仕上げるために、事前に用意されているsmall taskで具体的に何をどこまでできるようにすればいいか」という主体的な発想に変わります。
「練習」を経て「言語活動」に高めるには、活動を「自分ごと」にすることです。自分の考えを伝え合う、何かの目的のために必要な情報(または足りない情報)をやり取りすることです。
教科書の音読、英語の歌を歌う、ビンゴ、Q & Aなどは、「練習」の活動です。それを「言語活動」レベルにまで高めることが大事です。音読であれば、なりきり音読(登場人物やナレーターになったつもりで)をペアで考えるようにします。音読は、言語活動ではなく「練習」です。教師やデジタル教科書の後からただ繰り返すのではなく、場面を読み取ってどこをどう読めばいいのか、間を取るのはどこか、それは何故かを考えられるような指導が、音読を「言語活動」レベルに変えるのです。
英語の歌なら、特に好きなフレーズを使って身近な内容の英文を3文程度の文脈で書き、それを友達と紹介しあってコメントを言い合う。ビンゴなら、ビンゴになった生徒は、ビンゴになった列に入っている単語を使ってまとまりのある内容の英文を書く。それを次の時間に全員に配り、その英文を読んで質問をするといったことができます。つまり、「言語活動」とは、活動がどんどんつながり、4技能がリンクし、内容が深まっていくというイメージです。そして、生徒は「自分ごと」なので夢中になって取り組むようになります。それを見た教師は元気になり、もっといい活動ができないか、もっと技能を高めてやりたいと思うようになります。
ALTの仕事は「技能」(聞く力、話す力)をTT授業の中で高めること
小学校、中学校で英文を暗記し、決まったスキットを覚えて演じる授業をしていると、高校や大学に進んでから生徒たちが困ることが起こります。
「技能」を身につけて大学に入った生徒は、1年次からプレゼンテーションやディスカッションに積極的に取り組むので、ぐんぐん伸びていきます。それは、TT授業でチャット、Show & Tellなどのスピーチ、マイクロ・ディベート、グループ・ディスカッション、プレゼンテーションなどを経験しており、インタラクションが自然にできるからです。
一方、知識偏重の教育を受けてきた生徒たちは「入試の合格」が目標だったので、言葉を使うという体験が圧倒的に少なく、大学に来てから発表する学生たちを見て可哀想なほど落ち込んでいます。
TT授業でコミュニケーション活動をたっぷりとやってきた生徒たちは、英文(原稿)を書いて暗記するようなことはしません。それは「技能」ではなく、単なる暗記だということを知っています。暗記型で勉強してきた生徒たちは、グループディスカッションも全て事前に英文を書き、それを見ながら言おうとします。しかし、その時にはすでに違う話題に進んでいるのが常です。彼らはため息をつき、中学校の時にもっと話す活動を入れてほしかったと嘆きます。
臨機応変に(即興で)対応できる生徒を育てるのは、高校からでは間に合いません。小・中でTTの授業を中心に、コミュニケーションの下地(素地)を作っておかないとできないのです。
もし、葉っぱや枝(本時で教える教科書の内容)しか見ようとしないなら、木の形(単元で育てたい力)も森全体(育てたい力)も見えてきません。教師が「どんな授業をしたいか」ではなく、生徒たちがこれからの世の中で「どんなことができるようにならなければならないのか」を考えることで、木も森も意識できるようになります。そのためには、今のうちに何をしておかなければならないのかを考えられるようになります。そのことをALTと一緒に話し合っておくことこそが、本当のTTです。(本来、TTは生徒の技能を育てる協同プロジェクト)
しかし、ALTにはゴール(最後のシーン)が示されているでしょうか。仕事柄、ALTと話すことが多いのですが彼らからの相談として、次のように言われることがあります。
「食材(言語材料と語彙)だけ示して、来週の授業までに授業で使えるワークシートを作っておいてほしいと言われます。しかし、時間をかけてそれを用意しても、仕上がったものが違っている(教師が求めているものではない)場合、『私は八宝菜みたいなものをイメージしていたのに』と言われることがあります。いい人なんですが、授業については思いつきで場当たり的です。最初に最後のシーン、育てたい子どもの姿を教えて欲しくて、それをお願いするのですが、忙しいから無理、そんな時間ない、と言われます。でも、職員室では他の教師と雑談をして笑っています」
ALTをがっかりさせないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。
私が関西外大にいた時に「Team Teaching Activity Book 中学校英語検定教科書対応 Team Teaching 活動案集」(編著、出版インタラック)を出しました。その中の「はじめに」で書いた内容をご紹介しておきます。ALTの方と一緒にこれをお読みいただき、教科書を先に進むTT授業ではなく、生徒に「技能」を身につけ、自信をつけるTT授業について話し合ってみられてはいかがでしょうか。
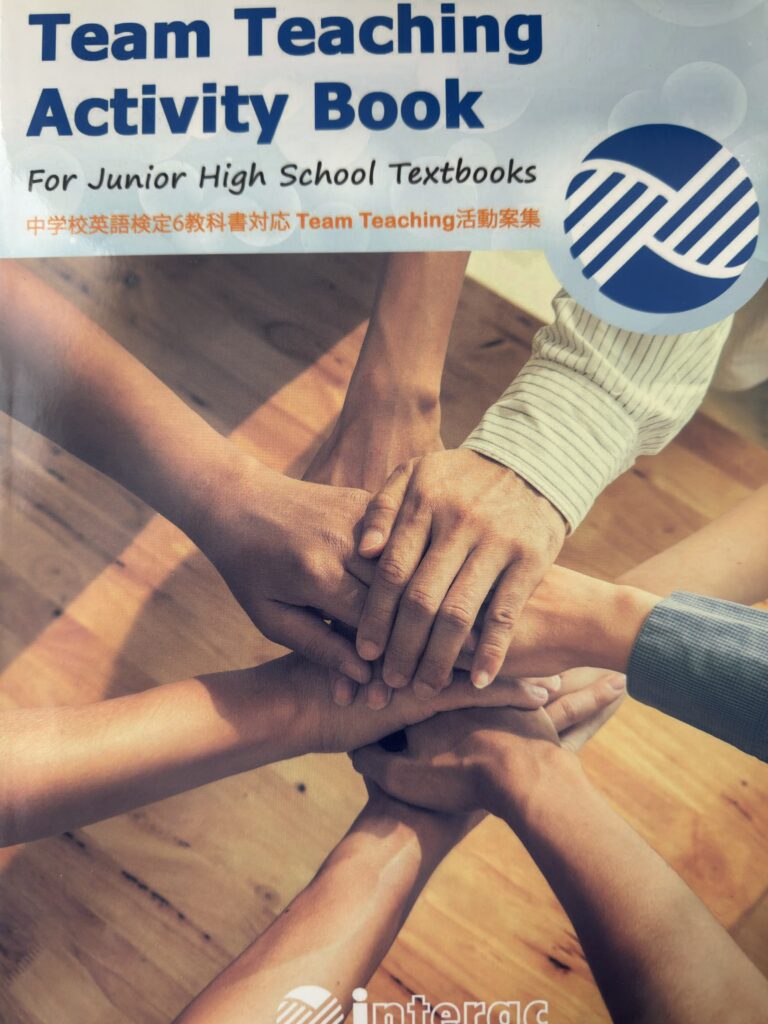
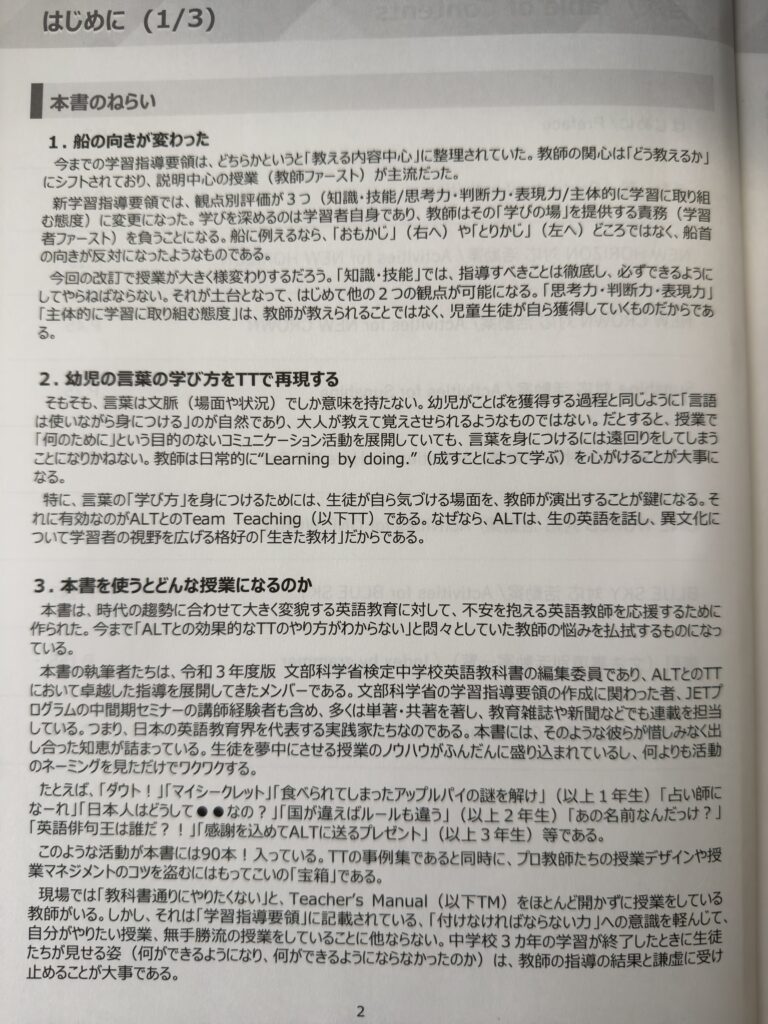
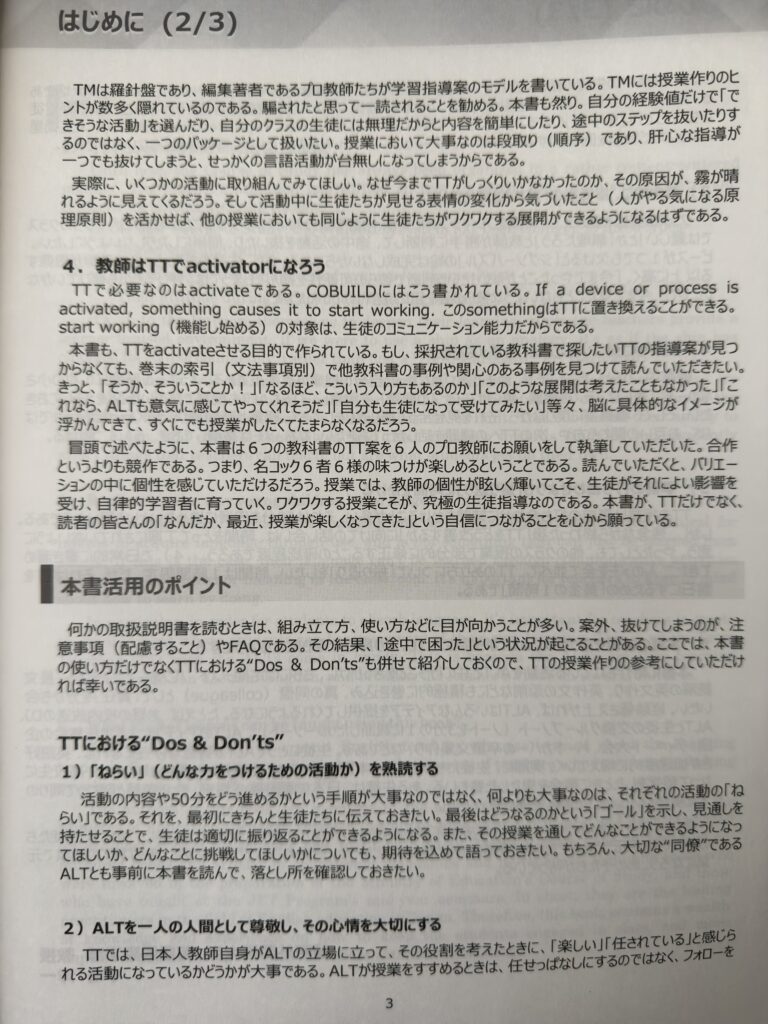
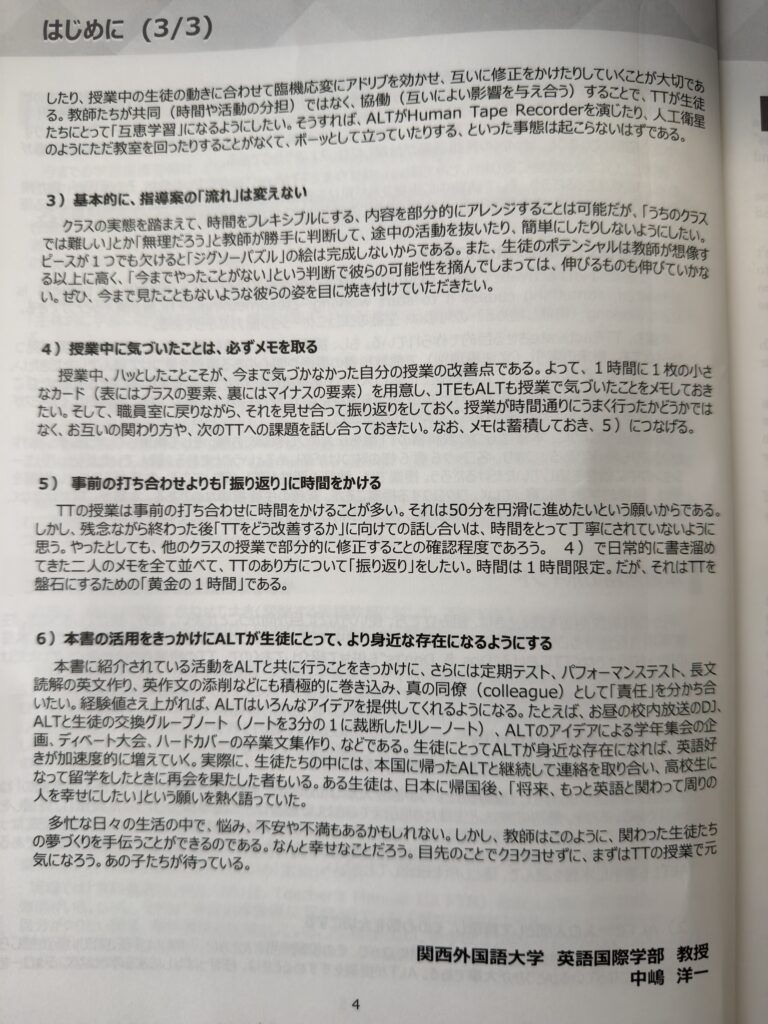
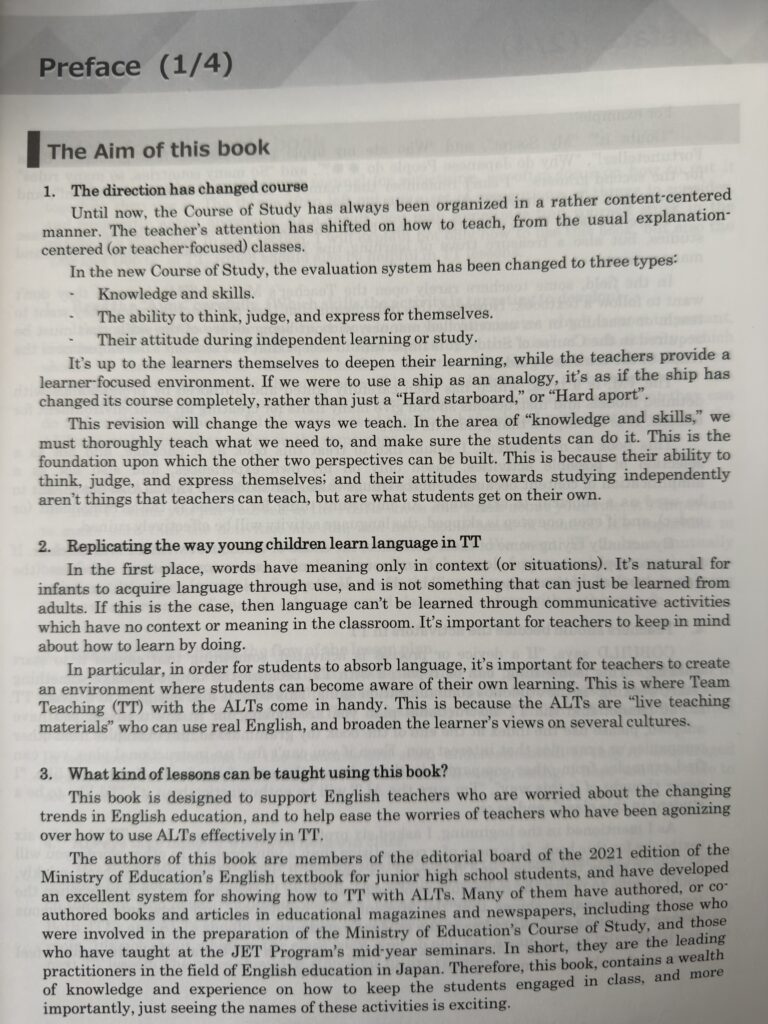
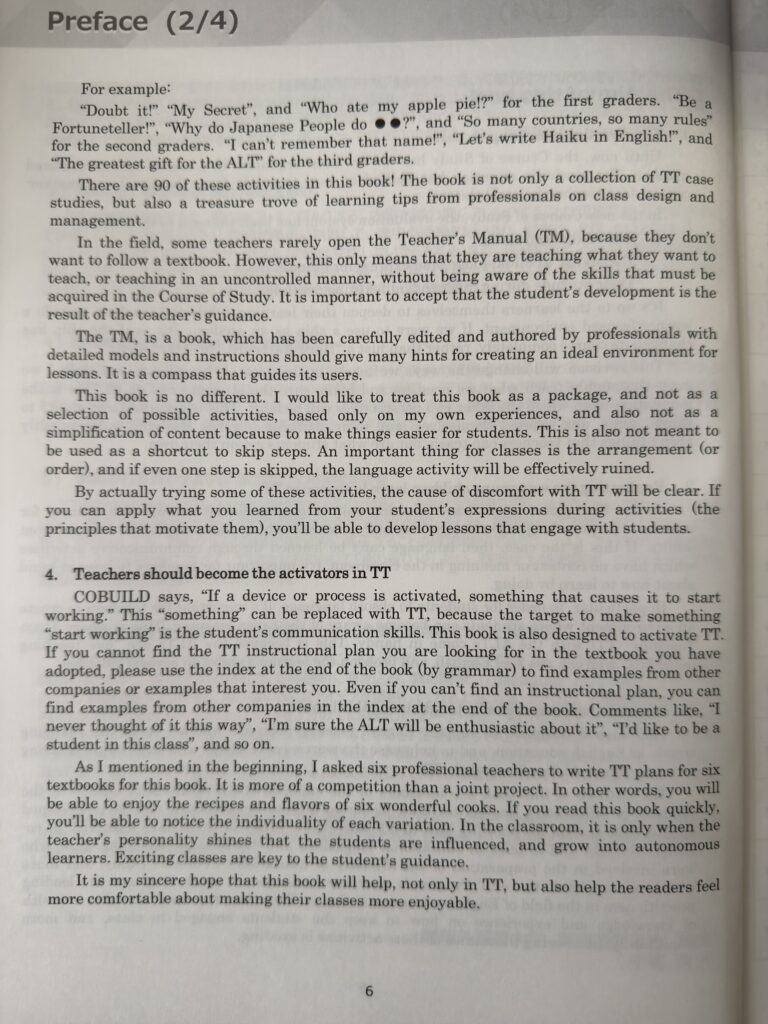
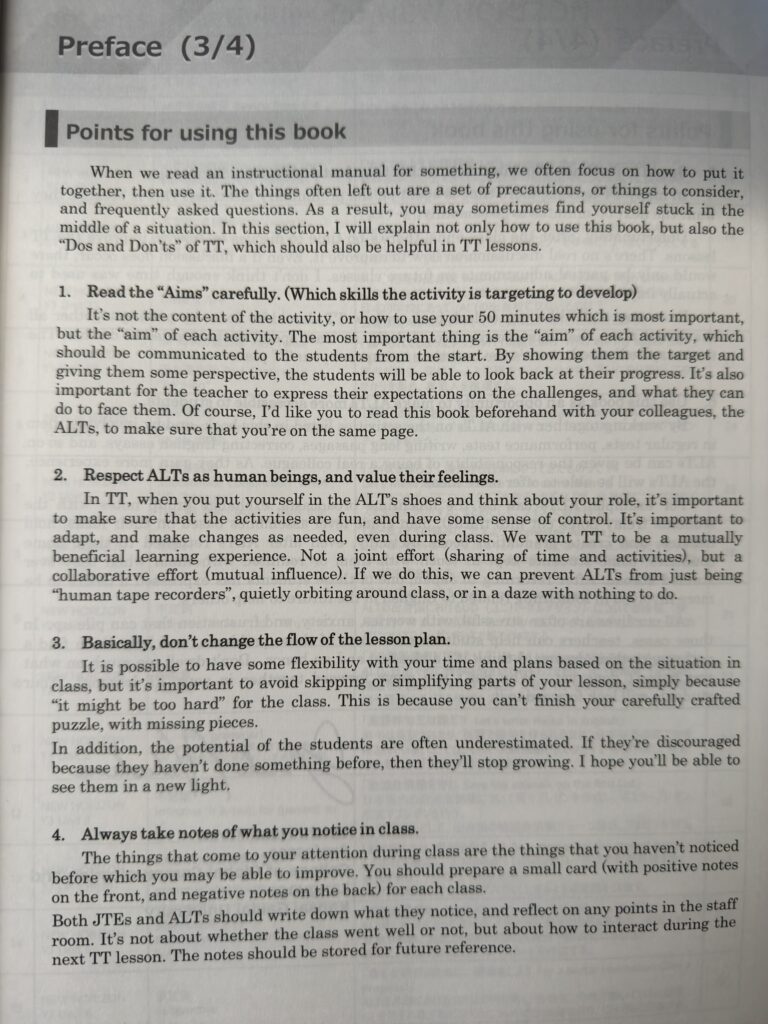
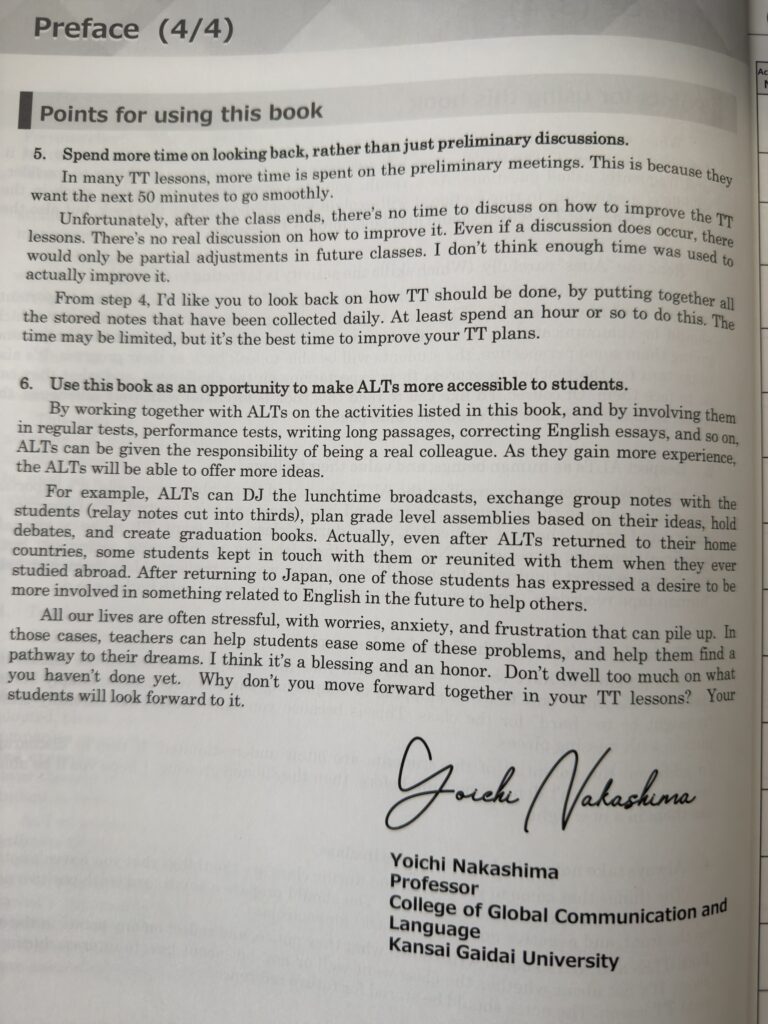
印刷用(こちらのPDFを印刷に使ってください)
日本語版
https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/05/Team-Teaching-Activity-Book-Preface_日本語.pdf
英語版
https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/05/Team-Teaching-Activity-Book_Preface_English.pdf








