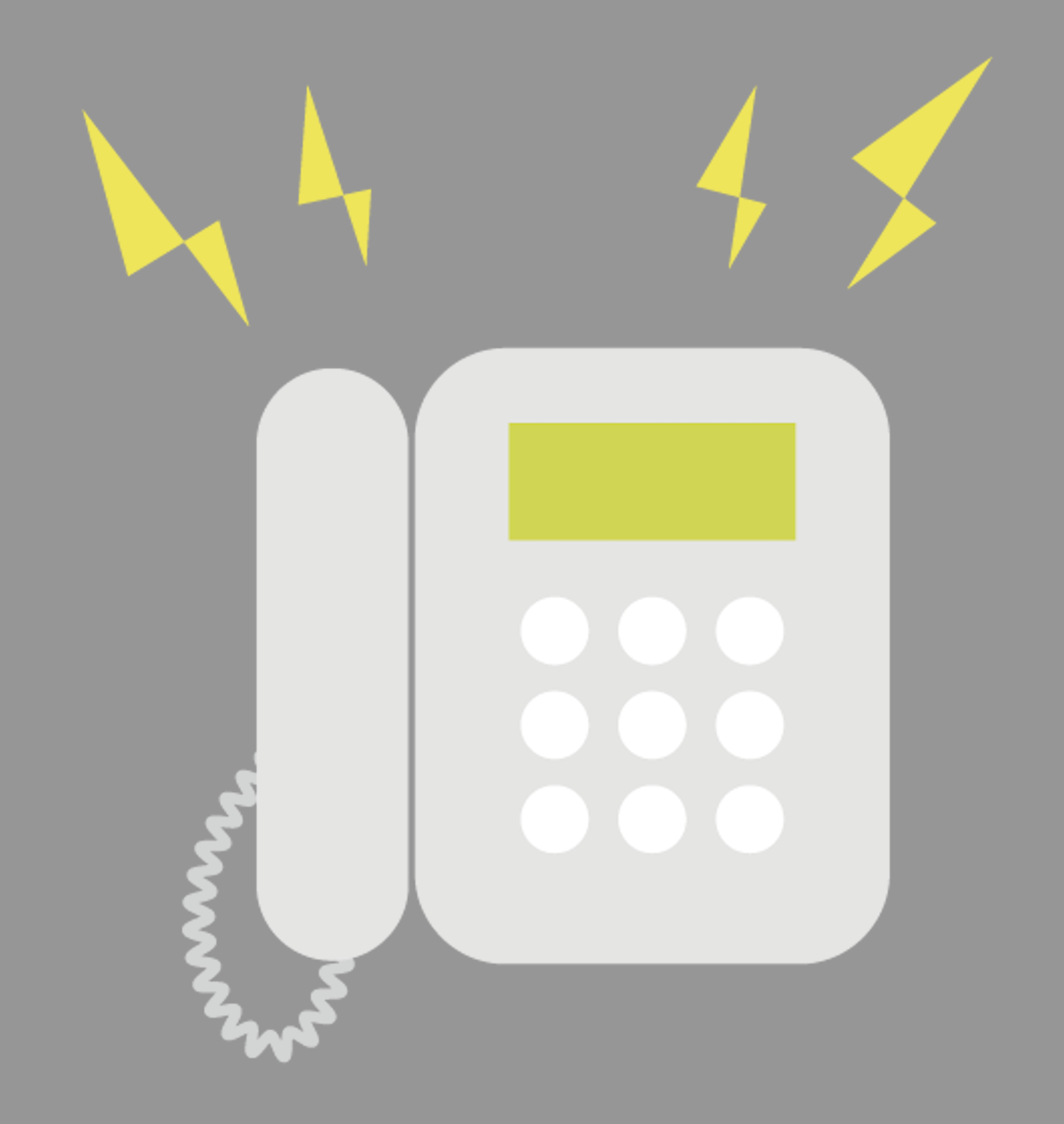◆ 実際に「活用」できるのは、本質を知っている学習者だけ
中1の教科書に「現在進行形」が出てきます。
教師は、目的・場面・状況を考え、「校区の小学校6年生に向けて学校紹介をしよう」という活動を仕組むことがあります。その中で「現在進行形を使って、様々な活動を紹介する」というものです。
ただ、これは、ご自身の体験(中学校で教わった時のこと)がイメージとして残っている、その影響が大きいと考えます。
しかし、そもそも、「現在進行形」は、何かが続いている状況のためにそれを止められない。つまり、頼まれたことができない」という場面であったり、「今、目の前で起きていることが自分が予期しないことや不愉快なこと」(What are you doing?)であったりする場面でよく使われます。それが、コミュニケーションの場面(言葉が使われる必然性があるシーン)です。
6年生に見せようとしている映像は、すでに「過去に撮影されたこと」です。ということは、リアルタイムではないし、単に紹介するだけなら、それについてやり取りが生まれるということもありません。つまり、コミュニケーションが成り立たちません。
また、授業を拝見していると、子どもたちのこんなつぶやきが聞こえてくることがあります。「これって、ホントにやんの?」「まさか、いつもの通り、研究授業用だろ?」いくら、リアルなテーマを考えても、実際にやらないのであれば、それはごっこ遊びと同じです。
子どもたちは教師が本気かどうか、ホンモノかどうかを見分ける力を持っています。
「人に見せるための授業」で終わらないようにするには、最後のステージ(小学生や小学校の先生からのコメントをもらって還元する)までを考えておくことが大事です。
私がこのHPでご紹介した蒔田 守先生(筑波大付属小)の実践を思い出してみてください。
「折り紙キング」と呼ばれている生徒が、他の生徒たちの目の前で実際に折り紙を折っていく様子をOHC(over head camera) で映し出しながら、それを先生がリアルタイムで英語で解説していくという授業です。
事前に撮った映像ではありません。Focus on Form (以下、 F on F)の見事な実例です。 F on Fとは、文法を最初に教えずに、場面を通して内容と使われている英語から学習者自らが思考を働かせ、現左進行形のニュアンス、さらには現在形との違いを掴み取る学習です。
https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2024/08/オンライン)①蒔田先生の授業(謎解き編).pdf
◆ テキストのスキットから学ぶ「リアルな場面」
SUNSHINE ENGLISH COURSE1年には、ネイティブたちが「実にauthentic だ」と絶賛した現在進行形のプログラム(平成14年度版、平成18年度版)があります。
ここでは平成18年度版をご紹介します。現在進行形のニュアンスがよく伝わってきます。
Program 10-1 A Busy and Happy Morning
ある家族の日曜日です。電話が鳴っています。
Mother : Sam, can you answer the telephone?
Sam : Sorry, I can’t. I’m busy now. I’m writing an email message.
Mother : Meg, answer the telephone, please.
Meg : I’m talking on my cellphone.
Mother : Jim, please answer the telephone.
Father : I’m sorry, but I can’t. I’m washing Victor right now.
Mother : Oh, my!
ちなみに、14年度版は、I’m drying my hair. / I’m changing my clothes. / I’m brushing my teeth.でした。いずれも同時進行で、それぞれの行為が続いている様子がわかります。
もし、現在進行形を扱うのであれば、ペア(または3人)でオリジナル・スキットを作り、それを成り切って演じるという活動が有効です。さらに、それに対して、仲間同士で「評価」(内容は自然な場面だったか、英語らしさ・ジェスチャー・間・抑揚などはどうであったか)をするようにします。そして、最後は、どのグループの取り組みが良かったか、それは何故かをきちんと振り返り、コミュニケーション能力につながるようにします。
私たちは、つい新しく学ぶ言語材料の形や「使い方」(language usage)を教えようとします。しかし、それは「泳ぎ方」を教えているのと同じです。
大事なことは、その言語材料が使われる「自然でホンモノの場面」を作り出し、学習者にそのニュアンスを掴み取らせること、自分なりにそのような場面を創出して実際に使わせること(language use)です。