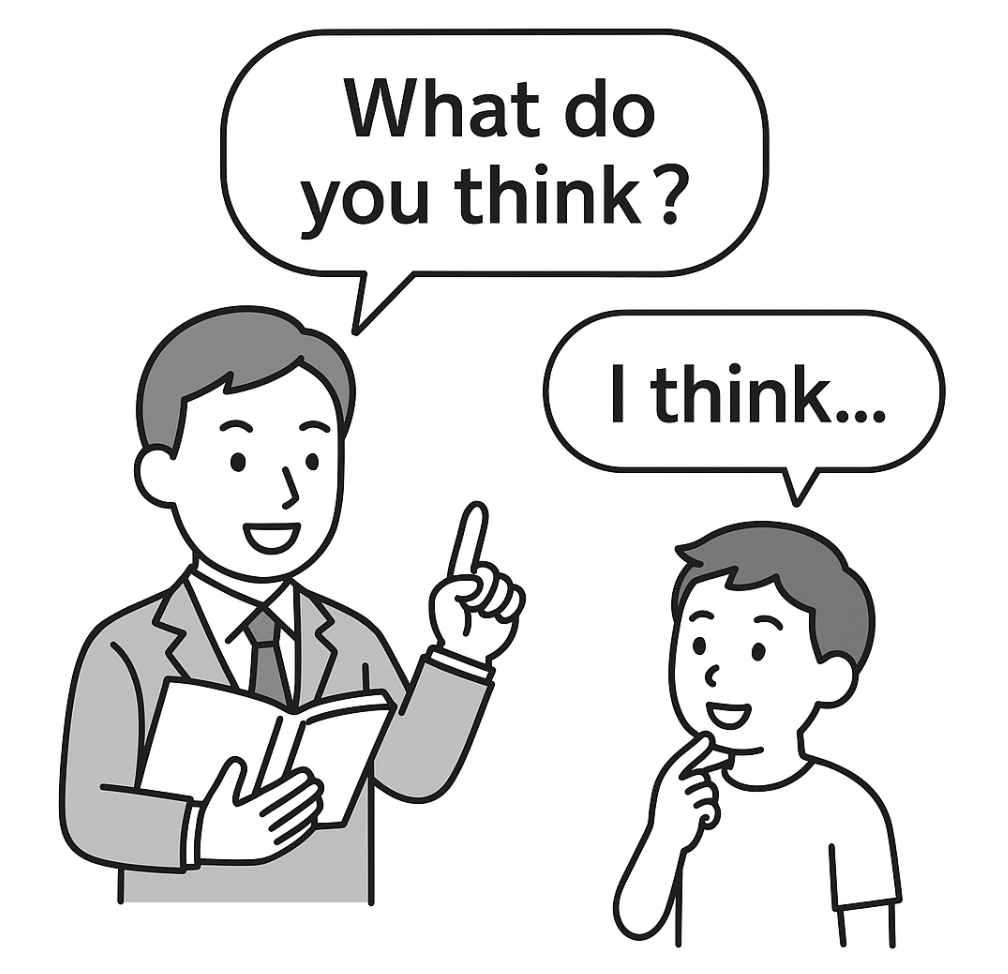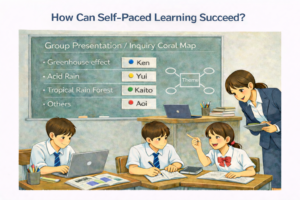📍 教師も生徒と同じ「学習者」
「学習者の英語力を高めるには、教師が英語を使って授業をすることが不可欠だ」──よく言われることです。でも、ここには少し誤解もあるように思います。
それは、教師が「英語で指示をする」、「英語を使って説明をする」のように「伝える側」、どちらかというと one-way で行なってしまうことが多いということです。
教師も、子どもたちと同じ「学習者」です。英語の「知識」についても「技能」についても、もっと高めていく必要がああります。子どもたちに教えるためには、それ以上に多くのことを学んで知っておかねばなりません。
つまり、教師は「より良い教え方」を求め続ける存在なのです。もし、昔つくったプリントやスライドを使い回してしまったり、一部だけ修正して使っていたりすると、それは“自己更新”を怠っているサインであり、結果として子どもたちの学びにも影響してしまいます。
📌 指示英語だけでは足りない
授業の中で教師が使っている英語を思い出してみましょう。
多くは「教科書を教えるための指示」や「発問」にとどまっていないでしょうか? 特に、“Repeat after me.”──このフレーズを何度も繰り返すことで、今までの自然なやり取りが、突然ぷつんと切れてしまうという場面をよく見かけます。
一方で、上手な教師は子どものつぶやきを拾い、そこから深掘りしながら自然なコミュニケーションを生み出しています。大切なのは「言語形式を教えること」ではなく、自然な文脈の中で子どもに気づかせ、考えさせ、英語での発話を引き出すことです。
では、具体的にどのように英語を使えばいいのかを考えてみましょう。
💡 英語を使う工夫・アラカルト
⑴ 前時のレビュー
授業の導入は「復習」から始めます。前時に学んだ表現を、身近なニュースやトピックに入れながら、本時で取り上げる表現につなげるようにします。生成AI(ChatGPT など)を使えば、30秒程度の“思わず聞きたくなるネタ”をつくることも可能です。次にご覧いただくのは、実際にChatGPTに指示(プロンプト)をした内容です。
中2レベルの英文、30秒程度の内容。つながりのある身近な英文、前時に習ったbetter than に加えて本時に学ぶ best も入れ、文脈から guess(推測)できるように、teacher talk を構成する。テーマは、食べ物編とスポーツ編で考えて欲しい。
次の2つの Teacher talk の原稿はChatGPTが提案したものを一部編集したものです。
🍰 食べ物編(Food)
Yesterday, the cooking club had a cake contest. They made a home-made cake and gave one piece to the teachers. It was so delicious!
Now it’s getting hotter every day. I want to eat something cold.
Which do you like better, an ice cream cone, a sherbet, or shaved ice?
(Shows the pictures)Ice cream is great in summer, but cake is better than ice cream for birthdays. However, what about Christmas? Which is the best for Christmas, an ice cream cake or a big fancy cake? What do you think?
🏀 スポーツ編(Sports)
Yesterday after school, I watched the third grade students playing basketball in the gym.They were running so fast, and they looked better than the city tournament last month.
Later, I saw the soccer club members playing in the yard. Their skills were much better than before, and their spirits were very high.
But for me, the best moment was when both teams finished and laughed together.
Sports are not only about winning. Friendship is the best result.
What do you think?
もちろん、生成AI(chatGPT)に頼りすぎるのは禁物です。しかし、それを使う目的は、あくまでも自分の英語力を高める(正確さ、豊かな文脈を学ぶ)ためであり、課題を代筆させることではありません。
Teacher talkでは、教師は「語り部」となって、写真や黒板の絵を使いながら進めていきます。「原稿」を覚えて、それを伝えるのではなく、子どもたちのリアクションを見ながら、適宜、Do you .. ? とか How many of you … ? というように問いかけ、巻き込むことです。ALT との TT も同じです。Teacher talk が終わったら子どもたちに感想を書かせたり、内容をクイズにしたりして、自然なインタラクションにつなげるようにします。
⑵ 帯学習(4技能を高めるプログラム)
練習を“流す”だけでは、やり取りは深まりません。
たとえば、子どもたちの small talk。ペアで一度話して終わりではなく、「気づいたことは?」「パートナーは何を聞いてきた?」と問いかけて振り返らせます。
そこから「じゃあ、これから1分間、内容を改善してみよう」と振り返る時間を与えます。相手を変えて、何度か繰り返すうちに、同じことを繰り返すことがなくなり、よりよくする視点が身についていきます。こうして、最初に立てたゴール──「何も見なくても、相手と深掘りをしながらやり取りができる」──に到達します。
⑶ 新出語彙・文法の導入
新しい単語や文法は、必ず「文脈の中」で紹介します。単発、フラッシュカードのみの練習では定着しません。言葉は、「場面」でしか意味を持たないからです。
たとえば、「クイズ形式」で新しい単語や文法を提示すると、自然にやり取りが生まれます。クイズ番組のMCのように、ヒントを出したり場面を想像させたりしながら進めるのです。
そして最後は必ず「自分ごと」に落とし込みます。
👉「今日習った文法や単語を使って、3文のつながりのある英文を書こう」
これを家庭学習のルーティンにしていきます。
⑷ 教科書の使い方
【読解編】
「事実発問」が7割、「推論発問」が2割、「評価発問」が1割。
授業では、基本的にこの割合で問いを準備しておきます。事実発問(fact-finding question)とは、本文中のthatやheが何を指しているかを尋ねるように、前後を見ればわかるものです。推論発問(Inferential question)は、本文を読んでいるだけでは見えない内容(行間を読み取らせるもの)です。そして、評価発問(Personal question)は、子どもたちの考えを発表させ、それをつなげていくものです。
子どもたちの「思考・判断・表現等」の力を伸ばすためには、彼らが夢中になるような推論発問、評価発問を吟味して用意する「教材研究」が大事になります。その2つの発問は「思考」をするための十分な時間が必要になるので、最低でも合わせて10分は取るようにします。教師がクイズ番組のMCのように、その間のやり取りが上手にできるようになれば、今までの授業が大きく変わります。
事実発問も、ちょっと工夫をすれば、子どもたちに「思考」させることが可能です。たとえば、内容を理解するまで各自で音読をし、その後、教科書を閉じさせます。
教師は、本文の内容を音読しながら、5W1Hの情報のところで、全体に問いかけるか、または個別に指名して答えを言わせます。
“The author’s friend came up to him and said what? Right. Then what did he do?”
こうすると、和訳をしないでも文脈に沿って理解していくことができます。指名されるので、どの子もただ音読をするのではなく、語順のまま理解するようになります。
【言語活動編】
教師が、子どもたちとのインタラクションを楽しいと感じるようになれば、さらに指導内容の軽重を図ろうとするようになります。「言語活動」(教師がお膳立てをしたり、指示をしたりするのではなく、あくまでも子どもが自己決定する、自分ごとになっている活動)に重点を置くようになっていきます。教科書のタスクも、「そのまま」使うのではなく、子どもたちと相談をしながら、内容をアレンジしてワクワクさせるタスクに変身させることができます。課題を選択式にすれば、子どもたちは「これならできそう!」と考えて取り組むようになります。「させられる」という気持ちがなくなるのです。教師は、子どもたちの活動中、座席表(学習カルテ)に気づきを記録し、後で教材研究に活かします。ALTとのTTでもお互いに、授業中見つけたこと、気づいたことをこの「座席表」に記録していくと、後で今後のTTの方向性を確認できるようになり、1時間のTT授業の分担を話し合うということがなくなります。
⑸ 授業のまとめ(Reflection)
まとめは「教師が代表の子どもの考えや作品をして紹介して終わり」という授業を見かけます。しかし、クラスの子どもたちは全員が、本時のねらいに基づいて学習をしてきたのですから、その到達度を「自己評価」できるようにしなければなりません。「メタ認知能力」を高めることが、そのまま「主体性」につながるからです。
そこで、子ども自身が「今日のねらいに到達できたかどうか」を具体的に「自分の言葉にする」ことが大事です。また、モヤモヤしている点も書かせましょう。できていないことを言語化することで、次のステップへのモチベーションになるからです。
ALT との授業では、ALT へのメッセージを書かせるのもおすすめです。ALT も次の授業で必ずそれに反応してくれるので、TT の質が一段と高まります。
⑹ 英語の歌(余韻を残す終わり方)
教師は自分で歌う必要はありません。リード役・盛り上げ役に徹します。
歌い終わると同時にチャイムが鳴る──そんな演出ができれば最高です。
最後は自然に “Good bye, class! See you tomorrow. Thank you!” と締めくくりましょう。
✨ リフレーズが教師の真骨頂
教師の力が発揮されるのは「リフレーズ」(rephrase)の瞬間です。COBUILD では次のように定義されています。
If you rephrase a question or statement, you ask it or say it again in a different way.
学習者がすでに知っている文法や語彙を使って言い換える。具体例を加えてわかりやすくする。それこそが、教師がリアルタイムで、英語で授業を行う上で真骨頂が発揮される場面です。
🎓 新里眞男先生からの学び
筑波の研修(1ヶ月)の折、元文部省教科調査官・新里眞男先生(元富山大学、元関西外国語大学)にこう教わりました。
「英語で授業を行う」とは、学習者の学習履歴を活かし、わかりやすく言い換えながら story teller のように語ること。そして子どもと自然なインタラクションを取ること。決して、一人で朗々と話すことでも、ネイティブのようにペラペラ喋ることでもない。
さらにこうも言われました。
もっと大切なのは、教師が話す時間を減らし、子どもが英語を使う時間──本当のコミュニケーションの体験──をたっぷりと与えることだ。
この言葉は、今も私の中で生き続け、公開授業を見る際の“指針”となっています。
🚀 自信につながる日々の実践
私は時間を見つけては、中学校の教科書3冊を徹底的に音読しました。ジュニア版英英辞典を使い、新出単語をクイズ形式で提示したり、派生語や生活に即した例を関連づけたりしました。
こうした習慣が「英語で授業を進める自信」へとつながりました。その経験は後に、開隆堂出版 Sunshine English Course の Basic Dialog(現 Scenes)に活かされていきます。
🌟 おわりに
教師が「英語を使う」というのは、自分が“悦に入って(自己満足で)話すこと”ではなく、子ども理解をベースとし、わかりやすく言い換え、インタラクションを生み出すこと。そして、子どもが「自分の言葉で話せた!」と実感できる時間を増やしていくことです。それこそが、英語の授業の「本当の価値」なのではないかと思います。