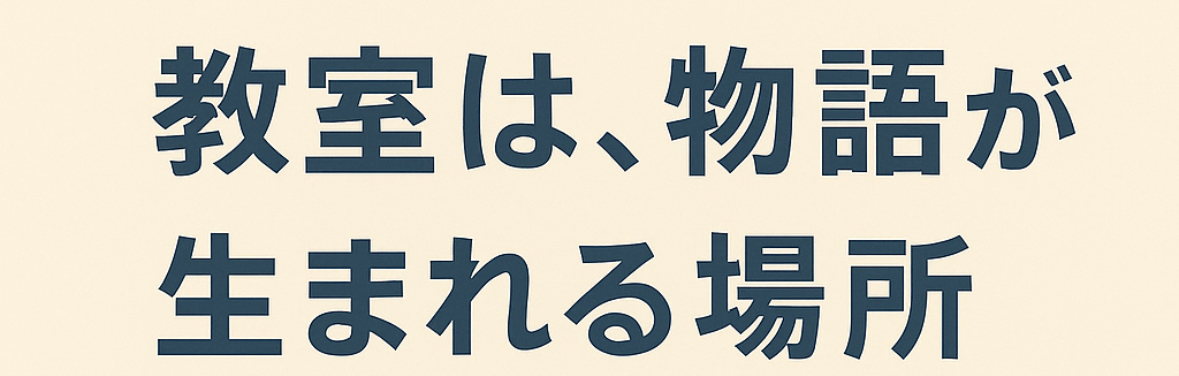*本稿は、来年刊行予定の直山木綿子先生(関西外大)との共著『4つの思考ツールで「広げる力・つなげる力・まとめる力・深める力」を高める言語活動』(仮)の一部を含む「予告編」です。
🎞 アニメと授業は似ている
海外を訪れるたびに、日本のアニメがいかに世界中で愛されているかを実感します。
シドニー駅の書店にも、ヘルシンキ駅の本屋にも、アニメ関連の書籍がずらりと並んでいました。
アニメの魅力は、ストーリーだけではありません。
観る人の心をつかむのは、“余白”――つまり「間(ま)」の演出です。
たとえば、
「この事件の犯人はお前だ!」を2コマで描く代わりに、「この事件の犯人は…」「(無言)」「お前だ!」と3コマにする。
その“無言の一瞬”に、読者は息をのみ、期待と緊張が生まれます。
クイズ番組でも同じ手法が使われています。答えの前の「3秒の沈黙」が、視聴者の集中を呼び覚ますのです。
🪄 授業も「演出」で動かす
授業が上手な教師ほど、生徒を動かすのは「説明」ではなく「演出」だと知っています。
「焦らしの間」を意図的につくり、子どもが自ら気づく瞬間を仕掛ける。
その時間こそ、学びが“自分ごと”になる大切な一瞬です。
教師が「間」を信じるとき、学習者は「主体的」に学び始めます。
🎬 教育もまた「アニメーション」である
アニメの滑らかさは、動かす「セル画の枚数」で決まります。
1秒間に24コマが標準ですが、宮崎駿監督やディズニーは倍近い数を使うことがあります。
だからこそ、キャラクターの髪や手の動きがまるで生きているように見えるのです。
授業も同じです。
教師の語り、板書、子どもの反応――その一つひとつの「場面」にどれだけ命を吹き込めるか。
それが、学びの深さを左右します。
教育とは、静止した知識を“動く学び”へと変える営みなのです。
📖 「説明」ではなく「体験」を描く
皆さんは、「ナラティブ」(narrative)という言葉をご存知ですか。
「ナラティブ」とは「物語」や「語り」を意味します。
授業の中で、「語り手」は教師ではなく、子どもたち自身です。
彼らが主人公となって、自分の言葉で「物語」を紡いでいく―それも “ endless” に。
教師の一方的な説明では、学びは動きません。
また、答えが最初から決まっている課題、探求できない課題では、子どもの目は輝きません。
それを象徴する例を、2つのシーンで比べてみましょう。
【A】説明型の文章
(あ~、ついてないなぁ)
私はとぼとぼ廊下を歩いていました。
そのとき、廊下の端であるQRコードを拾いました。
よいしょと紙切れを掴み、スマホを取り出しました。
「えっ!」
そこには驚くべき情報が書かれていたのです。
【B】体験型の文章
(あぁ~、今日の授業、全然うまくいかなかったなぁ…)
私は何度もため息をつきながら廊下を歩いていました。
ふと床の隅に一枚の紙切れが落ちているのに気づきます。端にはQRコード。
「なんだ、これ?」
気になった私はそれを拾い上げ、職員室に戻ってスマホにかざしてみました。
―― 画面に広がったのは、マンダラ・チャートのテンプレート。
そして9つのマスの真ん中に書かれていた言葉は――
「そうかぁ!」
その瞬間、私は思わず声を上げていました。
【A】は出来事を淡々と説明していますが、情景が浮かびません。
「ついていない」とは何があったのか?「誰にとって驚く情報なのか?」――
読み手は状況を想像できず、心が動かないのです。
一方で【B】は、読み手を場面の中に引き込みます。
息づかいが伝わり、感情が共鳴する。
それが「体験型ナラティブ」の力です。
「物語」とは、説明ではなく「想像の余白」によって生まれるもの。
その「余白」が、学びに“参加している”という気持ちを引き出すのです。
さて、そろそろ、夕飯の準備をしますが、
同じお寿司でも、「余白」があると、ほら、美味しそうに見えませんか。


(後編に続きます)