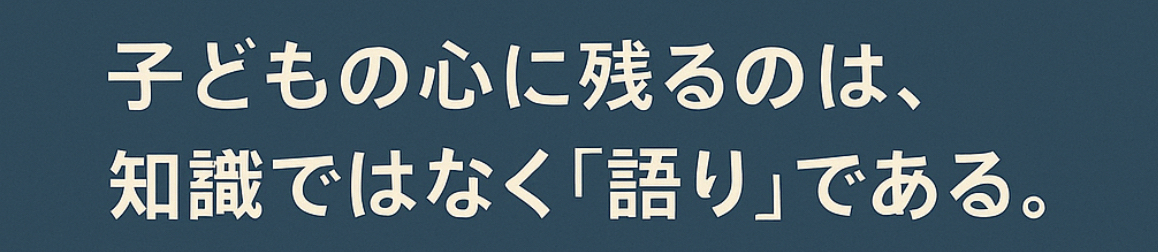✍️ 「空白行」は授業の“間”である
授業も文章も、“説明の連続”では息が詰まります。
文章の空白行は、読者に「息継ぎ」と「思考の時間」を与えます。
それは、授業における「間(ま)」と同じです。
空白を意識的に使える教師は、生徒の思考のタイミングを設計できる教師です。
導入の「つかみ」、展開の「揺さぶり」、そして終末の「回収」――。
すべてに“リズム”と“伏線”をもつ授業ほど印象に残るのです。
📚 「説明型」と「物語型」授業の違い
ここで、以前『英語教師の授業デザイン力を高める3つの力』(大修館書店, 2023)に掲載した文章を振り返ってみましょう。
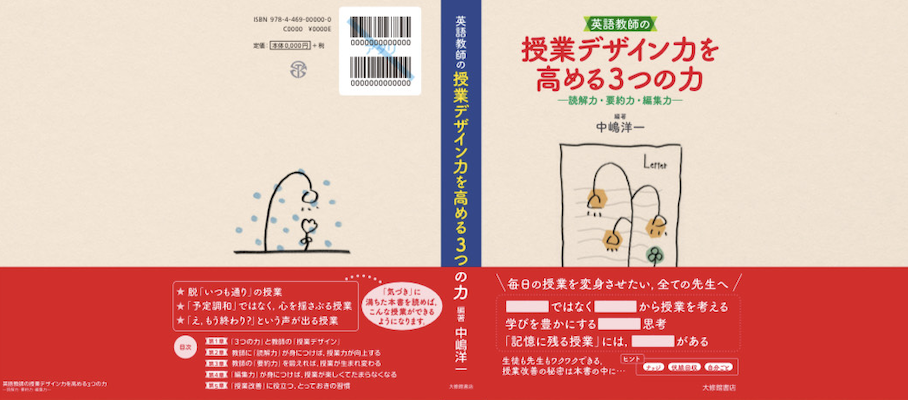
【C】説明型の文章
世の中には、失くすと困るものがいくつかある。財布、家の鍵、携帯電話などがそうだ。筆者は多くのものを失くしてきた。その度に冷や汗をかいた。しかし、今回ばかりは冷や汗どころではなかった。失くしたのは結婚指輪である。それに気づいてから3日間、血眼になって探し続けた。仕方なく、指輪を買った宝石店に電話をした。最後の手段である。手が震えていた。誰にも相談できない。日常から色が消えたようだった。そんな日々が続いた。そんなある日、見つかったのだ。車のシートの奥の奥からである。安堵でため息とともに瞳を閉じた。数日後、もう一つのそれは送られてきた。それは、そのまま押し入れにひっそりと眠っている。捨てたくても捨てられない。「高価なもの」だからだ。見せたくても見せられない。なかったものだから。これからもずっとなかったものでいてほしい。
淡々としています。内容は伝わりますが、読者の思考は止まり、感情も動きません。
いわば“説明型の授業”のようです。
【D】物語型の文章
「えっ?嘘! ない…。ないぞ…」
世の中には、失くすと困るものがいくつかある。
財布、家の鍵、携帯電話――これまでいろんなものを失くしてきた。
その度に冷や汗をかいた。だが、今度ばかりは違った。
失くしたとわかってから3日間、血眼になって探し続けた。
「ない、やっぱり…ない!」
放心状態になった。
そして、はっと思い立ち、そっと電話をした。
受話器を持つ手が震えた。
しばらくは、色が消えたような日々が続いた。
ある日、偶然、それが出てきた。
見つかったのは、車のシートの隅。
「あった!よかったぁ…」
ほっとした途端に、目頭から熱いものがこぼれ落ちた。
後日、電話で注文したもう一つが届いた。
「しまった、そうだった…」
何食わぬ顔で、そっと押し入れに隠した。
妻には口が裂けても言えない――「結婚指輪が2つある」なんて。
ここでは、書き手が「ナラティブ」となり、「物語」を演出しています。
導入で“つかみ”を作り、伏線を張り、最後に“回収”するリズムがあります。
これこそが、読者を引き込む「脚本構成」(デザイン)です。
授業でもまったく同じことが言えます。
この文章を書いた教師は、日頃から、最初で「つかみ」をとり、謎解きのような問題を出してぐいっと引きつけ、伏線を張っていく授業を心がけているのでしょう。途中、揺さぶりをかけ、最後にどんでん返しをする。「え〜っ!?」という生徒たちの声が聞こえてきそうです。
冒頭の問い(発問)は“導入のつかみ”
中盤のやりとりは“揺さぶり”
そして終末の「そういうことか」は“回収”。
そう考えると、教師は脚本家であり、演出家です。
沈黙の一瞬、黒板の一枚、問いかけの間――そのすべてが物語を動かす「コマ」になります。
🕊 教室に「余白」を取り戻す
最近の教科書は、QRコードや注釈、囲み記事でページが埋め尽くされています。
情報は増えたのに、逆に「想像の余白」(自由度)は減っています。
学びに必要なのは「全部を埋めること」(網羅すること)ではなく、
「立ち止まって考えるゆとり」であり「自分で判断すること」です。
プリントやテストも同じです。 文字がぎっしりの用紙を前に、苦手な子は息を詰めているかもしれません。 どの子も安心できる「呼吸」のスペースを用意する。
それに気づけること――それもまた「ナラティブ」です。
🎤 「沈黙」は、ナラティブの始まり
“Why do you think so?”
教師がこの一言を投げ、10秒ほどの沈黙を待てるかどうか。
その間、教室では確実に「何か」が動いています。
たとえば、肩が動く、視線が揺れる、指先がぴくりと動く――それらは「思考のサイン」です。
教師が「静寂」を恐れずに、それをじっと待ってやると、
子どもは安心して語り出します。
ですから、「沈黙」の意味を読み解くことは、ナラティブの始まりと言えます。
🧠 ブルーナーが示した「ナラティブ思考」
認知心理学の父と言われる、アメリカの心理学者ジェローム・S・ブルーナー(Jerome Seymour Bruner)はこう述べました。
「人は論理的にではなく、物語的に世界を理解する存在である」
この言葉は、授業改善の核心を突いています。
なぜなら、授業とはまさに「認知心理の世界」であり、子どもたちが世界を理解する過程を支援する営みだからです。
そこに必要なのは、教師の「説明」ではなく、子どもの「推測」や「連想」。
そこに学びが生まれます。
論理ではなく、物語によって人の心が動く――。
ブルーナーのこの視点こそ、「ナラティブな授業デザイン」の原点です。
🌿 「語り手」ではなく「共演者」として
「ナラティブな授業」とは、教師が「物語」を語るのではなく、
子どもとともに“物語を紡ぐ”授業です。
教師は解説者ではなく、物語の脚本家、舞台の演出家。
子どもを「物語」の登場人物にし、“コマ”を自ら描かせること。
それが、学びを動かすデザインです。
🌱 最後に
授業とは、知識を伝える作業ではなく、
子どもとともに「物語」を編む仕事です。
教師が子どもに「次のコマ」を想像させた瞬間、
教室は静止画ではなく、動き出すアニメーションになります。
教育は、文字に命を与える、生きた学びへと変えるアートです。
その瞬間、教室は「物語」の舞台となり――
子どもたちは、人生という“アニメ”の主人公になるのです。