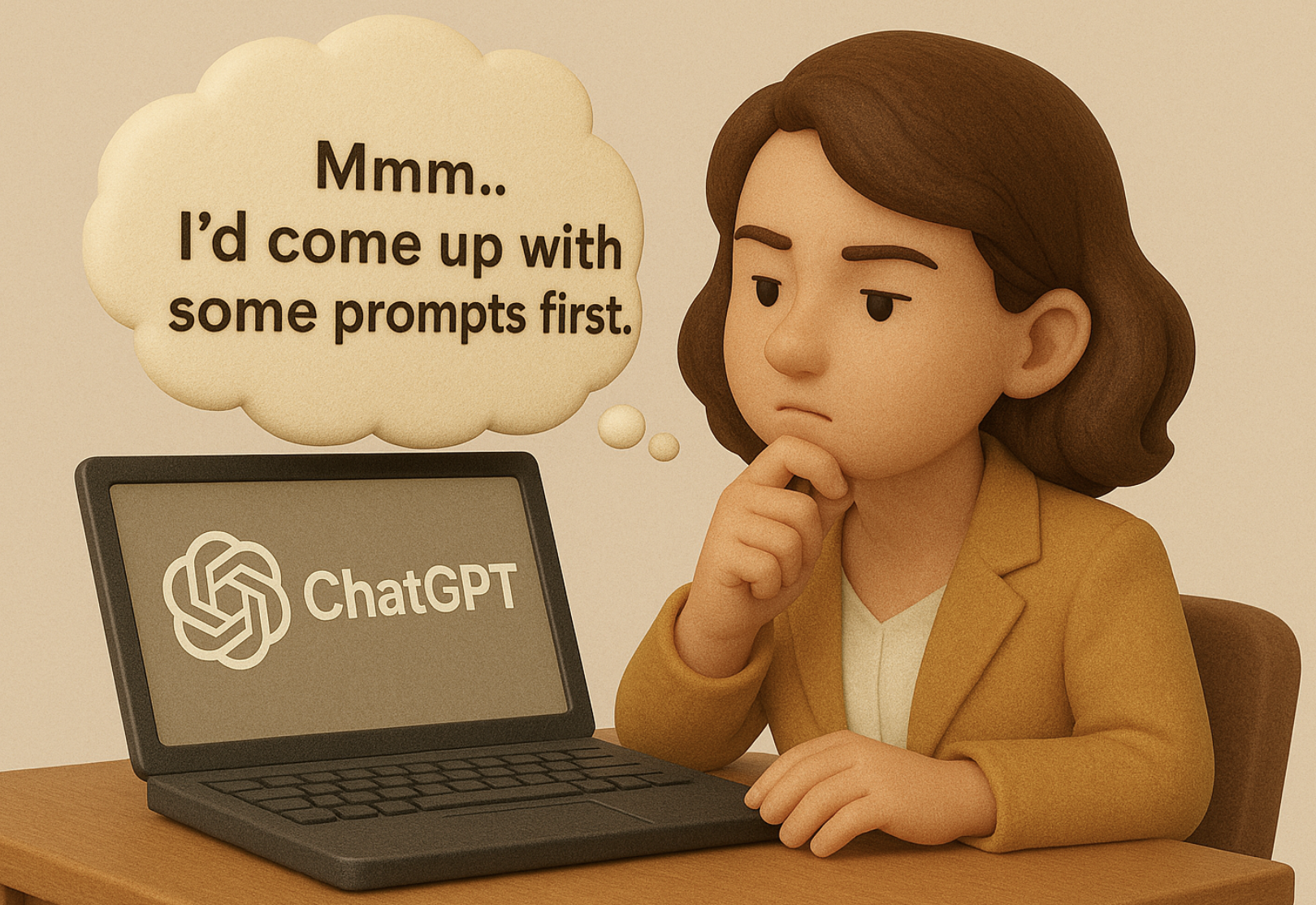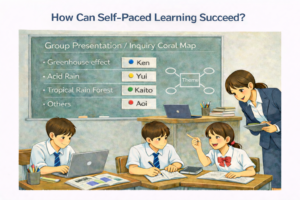◆「出力の場」をどうデザインするかが、これからの教育を決める
雑誌 Wedge 11月号の特集「未来を拓く『SF思考』停滞日本を解き放て」に、東京大学薬学部教授・池谷裕二氏の興味深い記事が掲載されていました。タイトルは「生成AI誕生で変わる未来、今こそ必要な人間の『空想力』」。内容の一部を引用します。
(引用ここから)
脳には「入力」と「出力」という二つの働きがあります。例えば、英単語を覚えるために繰り返し叩き込む行為は「入力」で、蓄えた情報をもとにテストを解くのは「出力」です。これまでの実結果から、記憶を定着させる2は、出力=テストを、手を抜かずに行うことが効果的であるとわかっています。入力と出力は両輪ですが、脳がどちらをより重視しているかと言えば、圧倒的に「出力」です。つまり、脳は「出力依存型」なのです。
…(中略)…
人間にはAIに真似できない力が数多くあり、その価値はこれからも決して失われることはありません。私は最近、学生に生成AIを活用してレポートを書かせています。数日かけてプロンプトを設計し、採点も生成AIに任せていますが、その評価基準は明確です。それは、学生の「個性」がどれだけ光っているかということ。つまり、レポート内容はAIに任せきりではなく、他者が思いもよらないオリジナルな発想がどれだけ反映されているかによって、点数が決まる仕組みです。普段から深く物事を考え、幅広く本を読み、情報に敏感であるかどうかが、得点に大きく影響します。
生成AIに頼りすぎれば、意見や発想が均質化し、社会全体の多様性が損なわれていく恐れがあります。また、AIのアイデアだけで生きていては、人は「生きがい」を感じることが困難になるでしょう。つまり、「生成AIがあるからラッキー」ではなく、「生成AIがあるからこそ、もっと深く学びなければ」と感じるべきなのです。そうなれば、人間の「個性」はもっともっと伸びるはずです。
生成AIに頼りすぎれば意見や発想が均質化し、社会全体の多様性が損なわれる恐れがあります。「生成AIがあるからラッキー」ではなく、「生成AIがあるからこそ、もっと深く学ばなければ」と感じるべきなのです。
(引用ここまで)
🌱「脳が喜ぶ学び」をどう作るか
私が強く共感したのは「脳は出力依存型である」という部分です。
自分の力で何かをアウトプットできた――その瞬間を、脳は一番うれしく感じる。
心身ともに健康でいるためには、脳を元気にすることです。
脳にとっての栄養は「出力」。
これは授業にもそのまま当てはまります。
私たちは、つい“教える”ことを中心に授業を設計してしまいます。
「教科書に載っているから教えなければ」ではなく、「どんな場面で使わせたいか」から逆算して考える。いわば input for output ――“出力のための入力”にすることが、学びを動かすエンジンになるのです。
授業で子どもたちの脳を喜ばせるには、「学んだことをどう使えばいいかを思考する瞬間」を用意することです。授業のゴールは「予定通り教えて終わり」ではなく、子どもが“出力”する場面を必ず作ること、そして子どもたちの「できた!」という笑顔を増やし、自信をつけることです。
🤖 生成AIは「教師力」を映す鏡
生成AIもまた、教師の「構想力」を映す鏡のような存在です。
同じようなプロンプト(指示)ばかり与えていると、AIもすぐにパターン化してしまいます。
ALTと同じで、ある意味、鍛えて、育てなければなりません。
生成AIは、まるで教師の話し方をまねる生徒のように、「この人はこういうことを求めているな」と学習するのです。
だからこそ大切なのは、緻密で意図のあるプロンプトです。
たとえば、
「中2レベルにして」といった単調なプロンプトではなく、
① 中2の既習内容で書き換える、
② 文脈の中で、discourse markerが必要な場所を5か所程度ブランクを作る、
③ 後でイラストを見ながらdescribeできるようにチャンク化する
――こう言うだけで、出てくる結果がまるで違います。
要は、生成AIに“仕事”をさせるのではなく、自分の授業構想をAIに反映させるという発想です。
生成AIは便利屋ではなく、あなたの構想を実現してくれる“共働者”にするのです。
🔍 ファクトチェックも「問い」で深まる
生成AIの情報は、かなり信頼できるようになってきました。
でも、そこで終わりにするのはもったいない。
読んでいて「ん? なんか腑に落ちないな」と思ったら、
「この部分の根拠を、臨床心理学の研究から探して」
とAIに尋ねてみるのです。
そうすると、生成AIの思考が一段深まります。
教育と臨床心理学はつながっている
臨床心理学は、人の心の働きや発達、ストレス、感情の扱い方を科学的に探る学問です。
つまり、教師が子どもを理解するうえでの「理論的な支え」です。
いま、学校では不登校、発達障がい、いじめなど、心に関わる問題が増えています。
そんな時代だからこそ、教師には「教える人」から「支える人」へのシフトが求められています。
🌾 学びを動かすのは「構想」と「理解」
AIも教育も、その根っこにあるのは「構想」と「理解」です。
教師が「どんな学びを構想するか」、そして「子どもの心をどれだけ理解できるか」。
この二つがハーモニーを奏でたとき、教室には――that moment (あの瞬間)が生まれます。
そう、脳がワクワクする“出力の時間”です。
そして、その脳の持ち主は、AIではなく、私たち人間なのです。