「演読」と“自分ごと化”で深まる英語学習
Sunshine がめざした「使える英語」のその先へ
前編では、Sunshine English Course の Basic Dialog がめざした
「先づけ × 後のせ」についてご紹介しました。
後編では、その理念がどのように授業で形になっていくのか──
「演読(えんどく)」「自分ごと化」「場面理解」など、現場で効果を
上げている実践をご紹介します。
1|「文法先行」の落とし穴
Q & A型授業は、インタラクションを生まない
文法を優先する授業では、教師はプリントを用意し、“説明→練習→確認”の手順で進めがちです。
しかし、この流れは次のような問題を生みます。
- 質問が Q & A型(正解当て) になりやすい
- 生徒が「多様な考え」や「ギャップ」に気づけない
- 学習者の関心が「テストで点を取るための答え」へ向かう
- “伝えたい”という感情が生まれにくい
つまり 英語の本質である“インタラクション”が起こりにくくなるのです。
2|「演読(えんどく)」が英語を“自分の言葉”にする
「ドラマ」を演じるように読む
一方、「伝えたい」を重視する教師は、教科書本文を “音読用の台本” としてではなく、
演じるための脚本(スクリプト) として扱います。
授業では次の流れで進めます。
- 台詞の意味・感情・状況を読み解く
- 文章の横に、俳優が使うような「ト書き」を書き入れる
- 役になりきり、感情を込めて 演読(演じながら読む) する
すると——
- セリフの裏にある「意図」を考える
- 相手の気持ちを想像する
- “伝えるためにどう言うか” を考える
という一連の思考プロセスが自動的に生まれます。
英語を“使う”ための心と技が同時に育つ のです。
3|言葉は「場面」でしか意味を持たない
文法は“今の状況”をどう切り取るかの道具
例えば「過去形」は、多くの授業で「動詞の形を変えること→それを覚えること」として扱われています。
しかし本質はそこではありません。
- 現在形:今わかること・習慣・性質
- 過去形:もう終わったことであり、今はそうではない/その時のことだけで、今はわからない
(=過去から現在へと視点の変化を伝えている)
つまり 文法は「時制の仕組み」ではなく「意味の道具」 なのです。場面を理解すれば、文法の意図は自然に見えてきます。たとえば、過去形の場合、指導は2通り考えられます。
◆ I am busy now.→ I ( ) busy yesterday.(be動詞の過去形を入れさせる)
◆ I had a lot of homework yesterday, so I was ( ) after school.
または
A: Are you OK now? You looked tired yesterday.
B: I was ( ) , so I went to the doctor. Now I’m fine.
のように自然な文脈の中でそれぞれ busy と sick に辿り着かせ「過去(今はそうではない)」のニュアンスを掴み取らせる方法です。
英語教師は、後者のように「学習クイズ」を提供し、子どもたちを思考を通してワクワクさせることが求められます。
4|町田市立金井中学校・栗橋ゆかり先生の実践
“My Before and After” が生徒の心を動かした
栗橋先生が扱った単元のゴールは、中学1年生による “My Before and After” プレゼンテーション でした。栗橋先生は3でご紹介したように、「過去形はどのように使うのか」という部分に焦点を当てた後、次のように単元計画(授業デザイン)をされました。
■ 言語活動(My Before and After)のデザイン
- スライド3枚(自作)
- 過去の自分
- 今の自分(変容した姿)
- その理由・きっかけ
- 絵や写真を必ず入れ、英文は入れない→絵や写真が伝えたいことのリマインダーになる
- ノートに英文を書かない→ 暗記ではなく「自分の言葉」で話すため
■ 深いインタラクションが生まれる理由
・“自分ごと”なので、仲間から自然に質問が出る
・聞き手が「もっと知りたい」と思える
・プレゼンターは質問に応じて内容を変えられる
最後は、グループ代表がクラス全体の前で発表+質問タイム を行います。
■ なぜ効果が大きいのか
- 場面(Before→After)で時制の使い分けが自然に理解できる
- 英語“を”学ぶのではなく、英語“を使って”自分を語る
- 文法ではなく 物語(Narrative) が中心にある
まさに、一人ひとりの英語が動き出す授業です。
5|Teachers’ Cloud の映像から見えるもの
Teachers’ Cloud(インタラックALT導入校向け)の映像には、
思考ツール
ペアワーク
生徒主体のインタラクション
などがふんだんに見られます。今回ご紹介した栗橋先生の実践も、そちらでご覧になれます。
映像を見ると、生徒が「伝わった!」と笑顔になる瞬間 が、はっきりとわかります。
【町田市立金井中学校 1年 過去形 最後の言語活動 My Before and After】
* 映像の肖像権については生徒、保護者とも承諾ずみです。
6|“Scenes”の例が示す「場面の力」
before/after で文法を使う必然性が生まれる
Sunshine English Course は、その後の改訂で Basic Dialogを “Scenes(2コマ構成)”に発展させました。基本文を自然な場面の中でより理解しやすくするための仕組みです。その代表的な例を紹介します。
【中2 must / mustn’t】
A: There’s some garbage here.
B: Oh, no! We must pick it up.
(次のシーンでは、花が咲いている場所にやってくる)
A: Look! This flower is beautiful.
B: Uh-oh, you mustn’t pick it.
→「状況に応じて義務と禁止が変わる」ことが場面で伝わる。
【中2 have to / don’t have to】
A: It’s going to rain.
B: We have to hurry.
A: We don’t have to. I have an umbrella with me.
(A が小さな傘を広げ、B はそれを見てため息)
B: I think it’s too small for us.
→ have to / don’t have to の自然な使い方が理解できる。
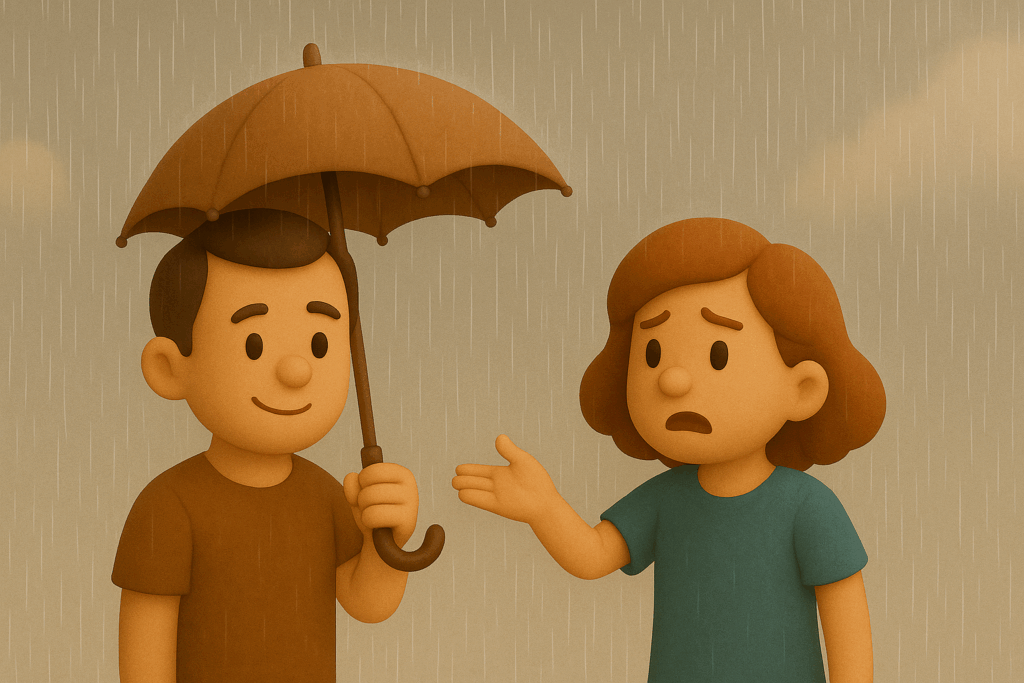
【中2 最上級】(前編のアイキャッチの内容)
A: I hate the rain. June feels like the longest month.
B: (雨上がりの空を見ながら)I think it’s the most wonderful month.
A: Why?
B: Because of that.(虹を指差して)A rainbow!
→ “最上級=個人の価値判断” として使われることがわかる。
【中2 不定詞(副詞的用法・形容詞的用法)】
A: I’ll go to New York to study dance.
B: Will you be a Broadway dancer?
A: Yes! I have a lot of things to do.
B: Go for it!
→ To V の意味(目的)が自然に浮かび上がる。
【中3 現在完了進行形】(後編のアイキャッチの内容)
A: I think Ami forgot about our meeting.
B: She’ll come soon.
A: We’ve been waiting for half an hour.
(B が遠くを指差して)
B: Oh, look! That’s Ami.
→ 「ずっと〜している」が、“待つ”という行動と場面にぴったり一致する。
7|「先づけ × 後のせ」の最終ステージ
生徒は“他者の物語”を聞き、自分を語り始める
英語の力がつく瞬間とは、生徒が 他者の物語に興味を持ち、自分の物語を語りたくなる 時です。
- 誰かの「Before / After」を聞きたくなる
- もっと知りたいから質問が出る
- 自分も語りたくなる
- 必要な文法や表現を自分から取りに行く
- いつの間にか英語が“自分の言葉”になっている
この循環が、最終的な学びの姿です。
「先づけ × 後のせ」は、生徒のナラティブを支える“学びのデザイン”である
まとめましょう。
- 文法先行の授業では、インタラクションが生まれない
- “演読”は、英語を“自分の言葉”にする最短ルート
- 文法は「意味をどう伝えるか」の道具
- Scenes の例が示すように、英語は 場面で理解される
- 最後は、生徒が “自分の物語” を語り始める
言葉は、本来「心が動いたとき」に使われるものです。
だからこそ、伝えたい理由を先につくり、必要な文法をあとからのせるようにするのです。
「教科書に載っている文法だから教える」から「言いたくなる場面を用意し、そこでどう文法を使うかを考える」という順序に変えるだけで、英語は「テストのための教科」ではなく、実際のコミュニケーションで使う「言葉」に変わります。








