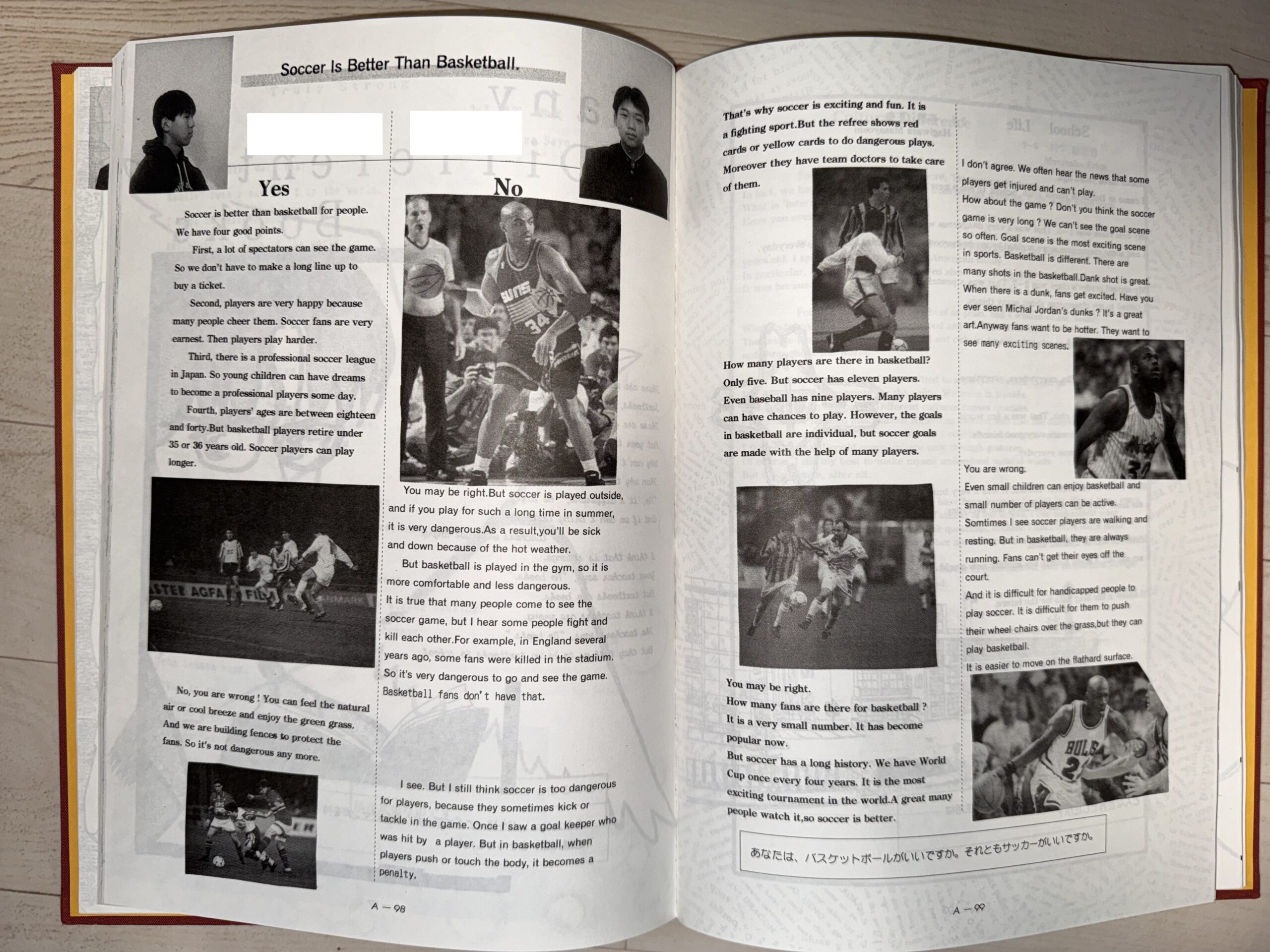オンライン交流は学習者を逞しくする
アイキャッチの写真は、1995年のAnthology(ハードカバーの卒業英語文集)の中のものです。私は1994年、国立教育会館の筑波分館で行われた「中学校英語教育指導者講座」(文部省主催)に参加しました。そこで出会った松本 茂先生(当時、神田外国語大学助教授。NHKテレビ英会話講師)の講座で、教育ディベートの発展性、可能性を知り、ワクワクしました。
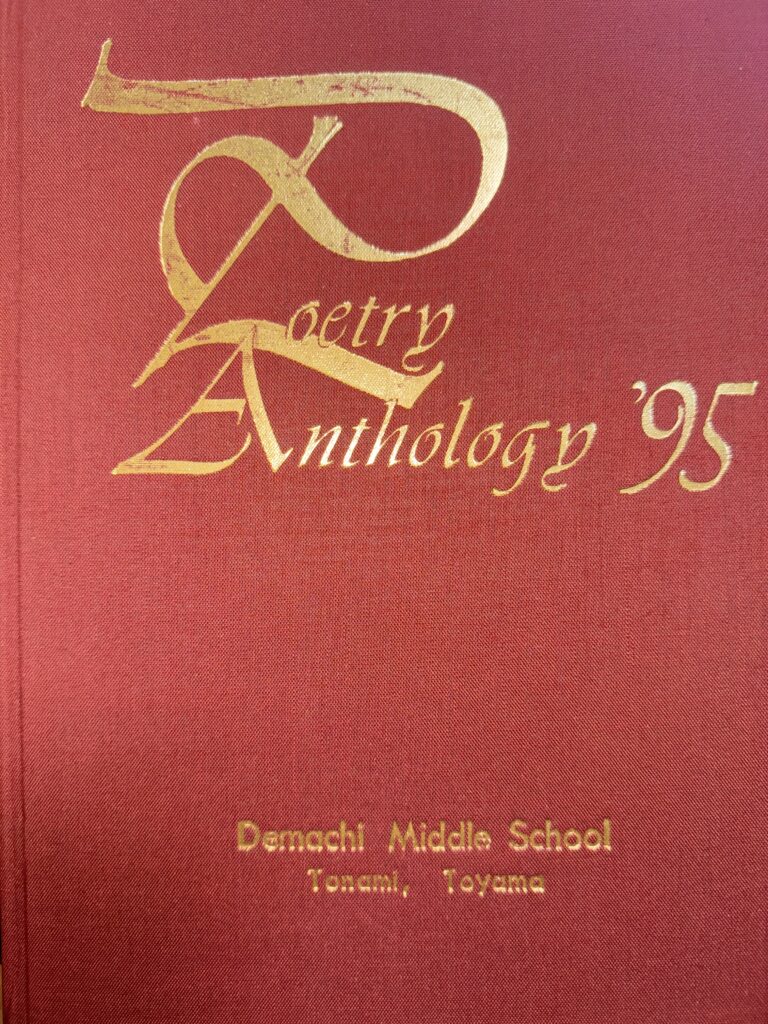
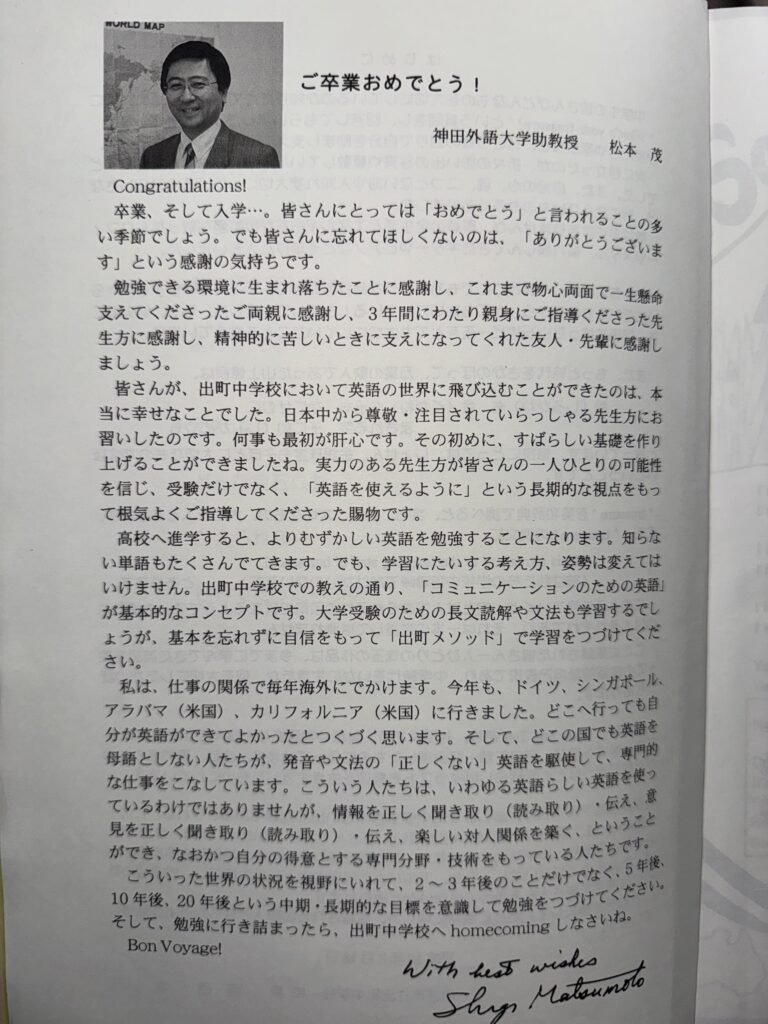
筑波での研修後、早速、3年生と2年生でディベートの指導をしました。1995年、1996年、1997年と試行錯誤しながら取り組み、1997年に仮説と検証をまとめた形で『英語のディベート授業30の技』(明治図書)を上梓しました。当時、まだ誰も「中学校で英語のディベートをする」という時代ではなかったので、驚き(と「本当にできるのか」という興味)を持って受け止められました。その後、「ディベートは難しい」という風潮はなかなか払拭することができないまま(優れた実践は数多く登場したのですが)、30年が過ぎました。
そんな私が、最近、ワクワクしたことがありました。2024年9月24日の記事(🟠教師は複数のものを「つなげ」、自らも「つながる」のが仕事https://nakayoh.jp/2024/09/24/)で、元中嶋塾@東京2023の塾生と元地球市民オンライン塾2023の塾生のコラボレーション(オンライン授業交流)をご紹介しました。
一人は本田大輔先生(東京都北区飛鳥中学校)、もう一人は八木一真先生(福島県新地町立尚英中学校)です。彼らはその後も交流を続け、3年生の最後にオンラインでクラス対抗マイクロ・ディベートに挑戦しました。
お二人から、「オンラインでマイクロ・ディベートをやりたい」という構想を聞いたとき、「いいですね!ぜひやったらいいよ」と応援しました。今まで、オンライン(skype, ZOOMなど)で英国の中学校、フィリピンの私立学校、ニュージーランドの小学校、台湾の中学校とつないでやり取りをするという授業を参観する機会がありました。ネット環境の問題で、途中で切れてしまうとか、事前に入念な打ち合わせが必要になるということで二の足を踏んでしまう方が多いようです。しかし、これからはそのような時代なのだと痛感します。同じ日本の学校同士でつながることも非常に有効です。お二人の実践はそれを証明してくれました。
ディベートで育てたい姿とは
「3年の最後はディベートができる生徒を育てたい」という2人の強い思いを形にするために、綿密な計画を立て、適宜擦り合わせながら構想を練られました。一人ではなかなかできないことを2人の協働タスクとしてはだてたことが、実践を可能にしたと言えます。
成功の要因は何だったのでしょうか。
まず、2人は教科書の文法や語彙の導入をインタラクションを通して行われました。つまり、文法や語彙の定着だけを優先させるのではなく、「技能」も同時に高める指導を展開されました。「インタビュー・マッピング」や「探究コーラル・マップ」を使って、情報を整理する、考えを形成することに真摯に取り組まれたことがそうです。
さらに、お二人はディベートを勝ち負けで終わらせず、納得解を重要視する「教育ディベート」に取り組まれました。最後はお互いの成長に感動し、相手への感謝で幕を閉じたのも、それらのことが影響していました。
オンラインで繋がった生徒たちが夢中になってディベートに取り組んだ
今回のオンライン交流・クラス対抗マイクロ・ディベートの指導として特筆できるのは次の3つです。
⑴ ディベートそのものを成立させることよりも、聞き取る、質問するという技能を鍛え、多面的かつ論理的に考えられるジャッジを育てようとした。(ねらいの明確化)
⑵中間指導(中間発表)を位置付け、相手の学校の生徒や仲間の良いモデルから学べるようにした。(主体的に学習に取り組む態度の見える化)
⑶「誰かのために」をモットーに「利他」の気持ちが生まれるような学習を推進した。(協働的な学びの具現化)
では、そのやり取りの記録(お二人によるレポート)をご紹介します。量が多く圧倒されるかもしれません。しかし、朱書きを入れながら読まれることをお勧めします。なぜなら、ディベートの指導を通して見えてきた生徒の「主体的に学習に取り組む態度」を育てるヒントが満載だからです。
オンライン・マイクロディベート(プロセス編)飛鳥中学校 本田大輔 教諭
https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/04/ディベートレポートプロセス編_北区飛鳥中_本田大輔-1.pdf
オンライン・マイクロディベート(生徒の成長編)尚英中学校 八木一真 教諭
https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/04/ディベートレポート生徒の成長編_新地町立尚英中_八木一真.pdf
実際の授業の「映像」(モザイク)を見てみましょう
マイクロ・ディベートの映像(肖像権のためモザイクを使用)をご紹介しておきます。最初は、初めてマイクロ・ディベートに取り組まれた飛鳥中学校(3年)の本田大輔先生の授業の様子です。彼は、「探究コーラルマップ」を使って、即興で論理的にやり取りができるように指導をされました。(レポート参照)
初めてマイクロ・ディベートに取り組んだ本田大輔先生の授業より(飛鳥中学校3年)
飛鳥中3年(東京)VS. 尚英中3年(福島)オンライン対抗_英語マイクロ・ディベート(11分編)
飛鳥中3年(東京)VS. 尚英中3年(福島)オンライン対抗_英語マイクロ・ディベート(21分編)
この21分編の”21分37秒”から”21分50秒”にかけての「心温まるエール」は、オンラインのマイクロ・ディベートを通して、お二人の先生が目指した「相手意識」(利他)を彷彿とさせるもので、ほっこりさせられます。ディベートを正しく指導すると、このような生徒さんたちが育つのです。
では、生徒たちはオンラインでの「ディベート学習」をどのように感じたのでしょうか。「感想」をご紹介しておきます。いずれも感動的です。
オンライン交流授業後のアンケートから
https://nakayoh.jp/wp-content/uploads/2025/04/交流授業(マイクロ・ディベート)後のアンケートより.pdf
ディベートは特別な指導が必要なのではありません。しかし、「単元で扱われているから」という消極的な指導では、「技能」も身につかないまま、形だけを教えることになり、「難しかった、うまく出来なかった」というストレスしか残りません。子どもたちが、しっかりとした「技能」を身に付けられるようになれば、「できた!」「できるようになった!」を実感できます。それは、自然に「もっとできるようになりたい」という欲を引き出します。そのような学習意欲が、全ての根幹となります。
ディベート(特に、マイクロ・ディベート)は、日常的にインタラクションの機会を増やし、「技能」を高める指導を展開していけば、最後は誰にでもできる活動です。実は、探究をベースにした「討論」こそが、夢中になって即興でやり取りできる力を育てるのです。
実際、ディベートを通して、生徒が英語での討議にのめり込んでいく様子を間近に見て「なんで、もっと早くやらなかったんだろう」と反省するようになり、その後、入力と出力のバランスが良くなります。今の授業がどんどん「学習者が主体となり、探究し始める授業」「学習者が楽しみにする授業」に変容していきます。