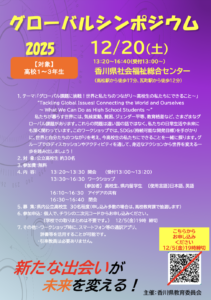見方・考え方が自然に立ち上がる単元計画の原則――主体的な学習者を育てるための必須事項とは
前編では、「見方・考え方」が育たないのは教師の努力不足ではなく、授業の入口(単元の設計)で“取り違え”が起きているという話を書きました。
後編は、その“取り違え”がどのような形で教室に現れ、そしてどうすれば「浮き輪を外した瞬間」のように、生徒の中に思考が立ち上がってくるのか――その原則を整理してみます。
結論から言えば、必要なのは活動の追加ではなく、単元計画に「思考の焦点(何を考えさせるか)」を埋め込むことです。そこが立ち上がった瞬間、教師が押しても動かなかった生徒が、自分で水をかき始めます。
現場で見かける授業のパターンをいくつかご紹介します。
◆ 活動はあるが、思考の焦点が与えられていない授業
授業を見ていると、次のような光景は珍しくありません。
- ペア活動・グループ活動はある
- ICTも使っている
- 教師は「主体的に」と声をかけている
しかし、何を考えさせたいのかが曖昧になっているようです。
たとえば、
- 教科書本文を読ませたあと
→「ペアで内容を確認しましょう」と生徒に委ねたままにする - Q&Aをさせているが
→質問も答えも教師主導で固定されている - 発表はあるが
→「正解となる英文」が言えたかどうかで評価している
このとき生徒の思考は、気づかぬうちに次のようになります。
「どう言うか」ではなく「正解かどうか」という意識になる
言葉は「場面」でしか意味を持ちません。相手によって使う表現も変わります。だとすると、多様な言い方が生まれてくるのが自然です。子どもたちは、「自分の考えた英文のどこをどう直せば伝わるのか」ということに関心があります。それこそが「思考」なのです。
しかし、入試に合格するためには「このように書かないと点数がもらえない」という指導になってしまうと、英語が「意味を理解し、伝え合う言葉」ではなく「正解を出すための対象」になってしまいます。
活動はあっても、自分ごとにならない―ここが、「見方・考え方」が立ち上がらない最大の原因です。
◆「文法理解=見方・考え方」と勘違いされている授業
次に多いのが、善意の努力が“別の方向”に積み上がってしまう授業です。
たとえば、
- 文法事項を丁寧に説明する
- 言語活動ではなく、練習問題の方がやたら多い
- 板書はきちんと整理されている
しかし、文法が“使われる文脈”がないのです。
中2であれば、 be going to の意味説明、例文音読、書き換え、正誤問題という内容は確かに漏れがない授業です。ところが、ここで育つのは多くの場合、次のような見方です。
- 文法=ルール
- 英語=操作対象
これでは、子どもたちの頭の中に「いつ・誰が・なぜそれを使うのか」という判断基準が形成されません。
知識は増えるのに、「意味で捉える見方」は育っていかないのです。
◆ 教師が先回りしすぎる授業
現場でなかなか「主体性が育たない」のは、
「負荷を与えて鍛える教師」よりも「丁寧な指導をする教師」の方が価値が高い
と勘違いされていることです。
教師が中心になって進める授業では、沈黙が生まれたり、時間が余ったりするのが怖いと感じるようになります。(攻めには強くても守りには弱い)その結果、指示や説明が多くなり、子どもたちは「指示待ち」「依存的(言われたことしかしない)」になっていきます。
生徒が言い淀んでいると、「つまり〜ってことだよね?」と教師から補足したり、表現に詰まると教師が即座に英語を提示をしたりします。
すると生徒は学習経験として、
- 考えなくても答えが出る
- 自分で整理する必要がない
という認識が生まれてしまいます。つまり、思考の主語が常に教師になってしまうのです。
これは「支援しない」のではなく、単元計画の中で“考えさせるための余白”を設計されていないことが原因です。
◆ 研究授業に多い「1時間完結型・打ち上げ花火型」の授業
参観者の目があると、従業者の関心は「いかに盛り上げるか」に向かいます。
ICT・協働・発表がてんこ盛りの授業です。生徒の活動は多いのですが、「活動あって指導なし」になり、ただこなしていくだけになります。このような「1時間完結型・打ち上げ花火型」の授業は、単元のゴール(最後の授業の学習指導案)が最初に作られていない(行き先が示されない「回送バス」に乗車させている)ことが原因です。
大事なことは、
「見方・考え方」は、繰り返し使われる中でこそ、自分で活用できる“型”になる
ということです。単発の活動では「見方・考え方」は定着しません。
研究授業ほど、単元の流れ(単元最後の授業がジグソーパズルの仕上がった絵のように細かく具現化されていること、前時・本時・次時の授業がのりしろで繋げられていること)を見せられるかどうかが問われます。
◆ 教師の指導が最も定着しやすいという誤解で行われる授業
教師は、スライドを用意し、丁寧な板書を心がけながら、繰り返し説明をしています。
しかし、初見の文になった瞬間に生徒の思考は止まります。
条件が少し変わると対応できません。
このような状況は、生徒が教師によって「見せられた(教師の)思考」をなぞっているだけだからです。
🍀 共通する本質:「使わせる前に、教え終えてしまっている」
これらの授業に共通するのは、
一人ひとりが「見方・考え方」に辿り着く前に、教師が型(答え)を与えてしまっている
ということです。
学習指導要領が求めているのは、「できるようにしてから使わせる」ではなく、「使いながら身につけていく」ということです。
つまり、単元計画の中に
- 何を見させるのか(焦点)
- 何を比べさせるのか(軸)
- どこで揺さぶるのか(問い)
- どこで言い直させるのか(再構成)
を埋め込む必要があ流ということです。よって、「見方・考え方が自然に立ち上がる原則」とは、
単元計画が「正誤」や「進度」ではなく、「視点」を育てることを目標に作成されている
ということになります。
単元計画で見取るべきは、
- 何と何を比べているかがわかる
- なぜその点で比べたのかが感じ取れる
- 伝えようとする意志が続いている
です。比較表現の単元であれば、評価の軸は「比較級で正しく言えたか」ではなく、“比較する視点を持って話しているか”です。形は後から整います。見方さえ立ち上がっていれば、指導と評価は必ず一致します。
🍀 授業中の見取りは「単元の途中」にこそある
「見方・考え方」が動くのは、テストの紙の上ではなく、授業の途中です。
次のような場面です。
- 生徒が比べるポイントを言い直した瞬間
- 他者の意見で自分の考えが揺れた瞬間
- 正しくないが「伝わった」と相手が反応した瞬間
このような場面をきちんと拾える(気づける)教師は、単元計画を立て直せます。
逆にここが拾えないと、授業はいつまで経っても「学習者がワクワクする」ものにはなりません。
高校の学習指導要領の中には、「適切に」という文言が繰り返し登場します。
これも授業技術ではなく、実は単元設計の問題です。
多くの場合、教師は授業中に
「相手を考えて」
「場面を意識して」
「もっと適切に言ってみよう」
と声をかけることで、何とかしようとしてしまいます。しかし、これではあまりに抽象的すぎて、生徒は「何をどうすればいいのか」イメージがもてません。
「適切に」は、その場の声かけや注意によって身につく力ではありません。この力は、状況が変わったときに初めて問われるものだからです。
同じ内容であっても、
・相手が変わる(友人、小中学生、留学生、地域の方など)
・目的が変わる(依頼、交渉、謝罪など)
・時間や形式が変わる(先、今、後、オンライン、電話、メールなど)
その瞬間に、
「この言い方では伝わらない」
「違うものから選び直さないと機能しない」
と感じる経験が、単元の中に組み込まれているかどうかが大事なのです。
ここで、生徒たちには「適切に」がストンと腑に落ちるのです。
重要なのは、「適切に」を文法的正確さの上位概念として捉えないことです。
本質は、「目的・相手・場面に照らして、言語選択を判断する力」の育成にあります。
「適切に」は、単元の中で、生徒が言い直さざるを得ない経験をどれだけ経験したかによって決まると言っても過言ではありません。単元を、比較可能な場面の連続として設計したときに、はじめて立ち上がる力なのです。
🍀 浮き輪を外すとは、「支え」を外すことではない
最後に、誤解を一つだけ解きたいと思います。
「浮き輪を外す」とは、支援をやめるということではありません。
「正解へ誘導する支え」を外し、“焦点に戻れる支え(思考の足場)”を作ることです。
つまり、
- 何を見ればよいか
- どこを比べればよいか
- 何を最初に言えばよいか
- どう言い直せば伝わるか
この「足場」が単元計画に埋め込まれているとき、生徒は不完全でも泳ぎ始めます。
そして、その泳ぎは、やがて高校で求められる「適切に」―
目的・相手・場面に応じて言語を選ぶ力へとつながっていくのです。